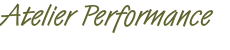現実批評としての身体─解体社「De-Control」から「混成への旅─Journey to Con-Fusion2」
立木燁子
ベルリンの壁の崩壊そしてソ連邦の解体で幕を開けた90年代は、混迷と急激な変化の時代だった。冷戦後の世界は、力による支配を超越するどころか、多発する民族紛争の結果、新しい矛盾を露呈させた。戦争、暴力、難民の問題など人間の営為の負の側面があらためて浮上した。しかし、象徴的なコソボ紛争が一応の終息を見せ、情報革命によって高速化された資本主義経済が性急に新たな世界秩序を求めつつある今、先進国と呼ばれる世界では現実の矛盾が表面的な富のイメージでとりあえず隠蔽されようとしている。その屈折した時代状況に、いま舞台表現は対応仕切れていない。現実の変化と複雑さを的確に伝える実験性に富む創造的な表現が獲得されていない例が多いのだ。
そんな時代にラディカルな政治性で強烈な存在感を示してきた清水信臣率いる日本の劇団、解体社が、複雑な様相を見せる今日の社会状況の中でそこに内包される危機をどう表象するか果敢に挑戦している。昨年の1月にはじまった新作のシリーズ〈De-Control〉、そしてメルボルンの劇団「NYID」(Not Yet It's Difficult)とのコラボレーションにおいて、人は本当に自由になれるのか、自他の関係をどう規定するのか、他者との共生は可能かといった根本的な問題について、身体表象を問い直すことで答えようとしている。
4月、5月、6月と続いて彼らの本拠、スタジオCANVASで上演された「De-Control V, VI, VII」はそれぞれに独立したパフォーマンスながら、文字通り、我が身に絡みついた<管理>の糸を解きほぐし、何が見えるかという統一テーマを模索する試み。当然、それは、直接、間接の管理に押しつぶされようとしている現代人への鋭い問いかけである。
4月の「De-Control V: many many」では、様々な支配と被支配もしくは強制と拘束(discipline)の身体イメージが提示される。後向きに立つ数人の男女。うずくまる女性を蹴飛ばす男性。激しく身体をぶつけあう(クラッシュする)男性たち。閉塞感のある小スペ−スに緊張感が漂う。 単純な動作の反復が動きに付着したステレオタイプ化した意味性を脱色し、抽象度が高まる。顔に覆面をし上半身裸の女性が自分の胸を押し上げてはジャンプする。数回跳ぶたびに脇の男性がその身体をリフトしては横にまわして倒立させるという所作が繰り返される。覆面は顔というアイデンティティ確認の通常手段を排除し、無名性の中に存在としての肉体を屹立させ、その表情の変化に観客の視線を集中させる。
アイロニカルな反転がここにある。単純な動作の反復による抽象化を通して強制と支配と見えた定型の読みが排除され、跳ぶこととそのサポートという行為にいつしか男女のセクシュアルな関係に似た共犯関係が浮かびあがる。顔を隠した無名の身体(=平等・固有な人間存在)に浮かぶ汗と身体表面に浮き上がる負荷としての疲労は、官能的な美しさへと転化されるのだ。覆面をとって普通の男女として認識される二人のダンサーが抱擁し合う場面では結晶化していた官能美が色あせて感じられてしまうのも面白い。
終盤、追う、捕らえる、強制という動きが象徴する抑圧的な力の前で、後手に縛られた女性に「名前は」という問いかけがされる。頭に包帯を巻き、傷ついた人の群れの向こう「オー、パワ−、オ−、パワ−」という叫び声のリフレインがかぶる幕切れには、清水信臣の危機意識がストレートに表れている。
身体所作の喚起するステレオタイプなイメ−ジに挑戦した「many many」での試みは、5月の「De-Control VI: 自由の虜」では、さらに徹底した直截の"行為"として検証された。数人の男女のパフォ−マンスは、互いに身構えあっては全力でクラッシュするデュエットの繰り返しが続く前半に、挑発的な背中叩きの場面が続く。上半身裸の女性の背中を平手でたたく場面は15分以上、白い背中に広がる赤い模様を目にし、背中を打つ乾いた音が耳に痛々しく響く。
パフォーマーたちは挑発的な行為も一種の儀式的な抑制感を保って行い、行為そのものの象徴性を浮き上がらせる。加害と被害の関係の中に「カタルシスを共有する感覚がある」と清水は語るが、彼の意図を超えて身体にまとわりついた社会的な意味性が浮上した。社会に根付く男性優位主義による支配・被支配の関係が男女の関係をも規定するという事実である。
6月の公演、「De-Control VII: 続S.M.3F.」はサディズム、マゾヒズム、フェティシズム、フェミニズム、ファシズムをめぐる身体イメージの考察。この公演では、様々な身体イメ−ジを追求しながら身体に刷りこまれた意味と束縛を解放する試みが行なわれた。覆面で顔を覆い自虐的に身体を壁にぶつける女性。痙攣する身体。激しくクラッシュする身体。女性=被抑圧者の構図を浮き上がらせた前回の問題が、男性にも身体を打つ行為をやらせることにより今回はより抽象化された。両腿を平手でリズミカルに打ち続ける行為は、反復の中で痛覚への刺激を鈍化させ、そこにまとわる社会的意味を脱色してしまう。いったん身体の抽象化を果たした後、ラストで群れとなった人々が巧妙に仕組まれた支配のシステムに収監されていく。壁に延々と映し出される歴代の天皇の名前の断片が、現実の支配関係をさりげなく示唆する手法も洗練されている。
独特のイメージの演劇を展開する清水の舞台で、あからさまな政治性が抑制され、抽象化された身体所作のなかに現代社会への問題意識が浮かび上がるところが巧みだ。「劇場には事実と行為しかない」とする清水のパフォーマンスで、かつてザグレブで観客を思わず制止行動へと走らせた直截な "行為" が突き付けるものが雄弁である。現実と虚構の境界をあいまいにするその手法は、緊張感をはらむ観客との濃密な関係のなかに強い演劇的磁場を成立させている。挑発的な身体表現に洗練度を加えて、同時代状況への異議申し立てを行なっている。
7月に森下スタジオで行なわれた解体社とメルボルンのマルチメディア、マルチカルチャーカンパニー「NYID」(Not Yet It's Difficult)と行なった国際演劇コラボレーション「Journey to Con-Fusion 2」も実験的で意欲的なパフォーマンスだった。
NYIDは芸術監督デヴィッド・プレジャーの独自の視点を活かした前衛的な活動が世界的に評価が高い。今回で二度目となったワ−ク・イン・プログレスのパフォ−マンスは二人の共同演出で行なわれ、テーマはメディア・テクノロジーだ。発展するメディア・テクノロジーが人間の欠落部分を拡張している一方で、個人は綿密に張り巡らされたメディア・ネットワークの中に絡めとられている。清水はここで「覗き部屋」「家族」などのモチーフを活かし、巨大なスクリーンに個人史を強制的に語らせられる俳優の表情を容赦なく映し出し、情報社会で個人の置かれた監視と検索の状況を暗示する。
「Shakespeare represent scolonialism. Sports is Fascism」と考えるプレジャーの演出では、大きな空間にマスとして俳優たちを動かす。「Work is Life, Life is Work」と唱えながら必死の表情で一団となって舞台をまわり続ける俳優達の姿には強迫的な緊張感があり、ファシズムの支配下に置かれた群衆を想起させた。ともにメディアを政治的なものととらえており、終盤、解体社独特の難民的な身体イメージの中で俳優たちが収監されスクリ−ンに天皇の名前が写し出される。観客たちも平土間に座り同じ空間を共有しており、現実感の強いパフォーマンスの中で情報社会の巧妙なシステムの下でプライヴァシーの部分まで支配されつくそうとしている現代人の状況がインパクトのある形で提示された。演出の方法論の違い、思想的差異の違いを踏まえて、今後のコラボレーションがどのようなものとなるか楽しみだ。
価値観が混乱している現在、演劇の創造性は現実の確かな認識を行なえるかどうかにかかっている。現代社会の閉塞感をラディカルな身体表現で表現する解体社の今後が期待されるこのところの活動である。
シアターアーツ14/ 2001年/8月