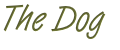西堂行人
世界の終わりへの空虚な感覚が本気とも冗談ともつかぬレベルで進行した八十年代――その好例が北村想の『寿歌』(七九年初演。東京公演は八〇年)ではなかったか――に対して、九十年代は、のっぴきならぬ歴史と対面することを要請してきている。そのような段階にようやく到り着いた。昨今、「リアル」なものの回復――決して形式としての「リアリズム」ではない――がめざされているのも、これを歴史とつなげていく回路が探られているからに他ならない。こうした現実感覚に導き出された舞台が、たとえば第三エロチカの『東京トラウマ』や解体社の『TOKYO GHETTO』『オルギア』ではなかったか。
タイトルに同じ都市名が冠せられた二つの舞台に共通するのは、東京という無時間都市がますます世界の危機にさらされはじめたという感覚であり、そこに生きるわれわれの皮膚感覚を直接性として描こうとするものである。その際もちいられた演劇の話法は、物語という虚構をもはや再構成しない。現実の断片がゴロンと転がるものに「局部対応」(別役実)するものだったと言っていい。
解体社の舞台では『TOKYO GHETTO』より、むしろ『オルギア』について触れたほうがいいかもしれない。東京芸術劇場中ホールのプロセニアム空間で上演された前者は、美学的なイメージの演劇としてはなかなかよくできたものと言えるが、ためにかえって彼らの劇のもっている質が伝わりにくかったかもしれない。後者は、「犬」の目から見られた世界を再構成したものである。そのなかで、いくつか印象に残った場面を紹介してみよう。
この公演はフランス座というストリップ劇場で上演されたが、冒頭十人近い女優達がどこからともなく現れ、やがて客席のなかに突き出した花道から出べそにむけて歩を進める。観客の視線に身をさらし、その視線が彼女らのからだを撫でまわすのを確認すると、やおら突き放すのである。ストリップという、まさに視線の悦楽を前提とする芸能の制度を逆手にとり、被視姦者たちからの逆襲をこの劇は企図している。
目隠しと口にテープをはられた女優が上半身裸のまま椅子に縛りつけられている。そこで声にならない声を発する。だがその声は分節言語(セリフ)として客席に届けられるわけではない。むしろ言葉以前の音、言葉に昇華される以前の叫び、吃音に近く、それは肉体の在りかを強く意識させる類のものである。ちょうどアントナン・アルトーが分節言語を拒否して魂の叫びを称揚したように。だが一九二〇年代のアヴァンギャルディストと解体社の言語以前の肉体が決定的に異なるのは、一方が詩人の純粋な精神を希求する叫びだとすれば、他方は言葉すらも奪われた情報化社会のソフト・ファシズムに対抗するイロニーに他ならないからである。
言葉が削られる。どんな言葉を発してもその言葉が射るべき対象は見出せない。したがって情報洪水に立ち尽くすわれわれは寡黙にならざるをえない。その寡黙によって現実を見返すこと、解体社の舞台が言葉に頼らずとも、現実の目に見えない拘禁状態に労働にも近い行為で手触ろうとしていることは明白だ。寡黙に投げ出された肉体こそが、ナマの現実に拮抗する。
シアターアーツ 1996年2月 No.4