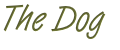痛みをわたしの肉体に刻むことを欲望して…
長谷川 六
劇団解体社は、1994年5月から7月にかけて『THE DOG』三部作を上演した。
二部作目の『A LITTLE STORY』に訪れると、十字架の形のモルタル塗りの舞台があり、防護用のネットを張った壁が立てられて6月だというのに会場に入ると冷気が漂っている。そっと客席を見まわすと、舌足らずの特有なエロキューションで周囲と関係なく会話している無神経な二人の若い女を除くと全員が男の客で、寡黙にこの空間がもたらす空気に浸っている。最近はどこの劇場でも聞かされる、時計のアラームのスイッチを切って欲しいというアナウンスが入るが実に納得する。
解体社の「劇」の筋書きを記すのはわたしには困難である。男(老人)の幼年期への追憶シーンが構成されているようだが、ゆっくり歩きや舞踏、劇が交互に現れ、わたしの時間は凝縮して彼らに吸い取られてしまう。残るのは老いることの悲惨と恍惚の至福で、わたしの貧しい言葉では言い表す事ができない。深い感動の中にわたしは沈んだ。
最終作『聖オルギア』には、さらに感銘した。「ここは路地裏のコロシアムークラブオルギアー老いた雌犬に夢見られた天国」と台本にあるような、決定的に異化された空間と演技者が存在した。肉体から剥ぎ取られるおびただしい怒りと情念と愛憎が、彼らが肉体と同様に価値を求めている彼らの絶対空間の中に放出され彷徨い出ているのに胸が痛み、その痛みをわたしの肉体に刻むことを欲望して、沈黙がこの場合もっとも有効な手段だと思って終焉と同時に劇場を後にした。
彼等の場合、語りは必ずしも言語に頼らず肉体からのものが多い。彼等は演劇として成立していて、前号でも書いたようにダンスとは多くの点で立場が異なるが、一つだけ指摘すると、作・構成・演出をしている清水信臣が気が付いていないのがスキルの問題で、ここだけが未解決である。
わたしが最初に彼等に出会ったのは檜枝岐パフォーマンスで、川の中を黙々と溯る姿だった。測量機を持ち水を足で掻き分けてゆっくり歩いていた。その後、鎌倉の校舎の中で侘びしさの限りを尽くすような舞踏を見たことも、檜枝岐で今度は滝を溯るのを見たこともあるが、彼等に何より感動したのは大船のモノレールの駅の廃墟で行われたパフォーマンスで、片側の駅に鉄板を配置して、摩擦によって火を起こすというもの。「異化」をこのときほど強く意識させられたことはない。まさに駅は鉄と火の限りなく放逸な、カフカでさえ書ききれない孤独な空間として、反対側のプラットホームで見るわたしたちの眼前にあった。
清水信臣の演劇は、パフォーマンスアートと限りなくボーターレスで、そもそも彼は区分上のスキルには関心がないように見える。情景と直感が織り成すのが清水の「劇」で、彼は何者にも囚われない自由と、そして「劇」という不自由を所有している。彼のテキストは彼自身で、彼が肉体で指し示す「檄」の静謐さはアンビバレンツさゆえに、誰の心をも捕らえて離れない強烈さをもつ。
ダンスワーク No.49 1994年10月 Dance Research Tokyo-5