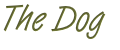'94年度上半期、心に残った舞台
西堂行人
演劇でありながら演劇以外の観念と結びつく。そうしたことを考えさせられたのが、解体社の『THE DOG』三部作だった。昨年本郷に開設されたアトリエ〈本郷DOK〉で三本の連作が五月から毎月三週間にわたって上演された。
『THE DOG』は文字通り、犬から見られた世界の断片を並べたものであり、物語のように時系列でみることはできない。むしろこの〈場〉に積層していくイメージをよりどころに観客が各自の想像力で自在に世界を組み立て直していくよりほかない。観客はかなりのイメージの飛躍を必要とする。だがそれは同時に、観客の〈解釈〉の自由度を最大限に許すことの表れでもある。
解体社の旗揚げは1979年だから、かれこれ十五年のキャリアを誇る。現在の主宰者の清水信臣になってからでももう十年近くになる。この間、この劇集団の作業は、身体に強くこだわりながらも、次第に劇の想像力を空間やオブジェ、音楽性などに押し拡げていった。野外での公演形態を模索していた時期は、〈場〉の強い吸引力に拮抗する俳優の身体を研ぎすまし、ことに男優たちは野外の空間をこの身一身で引き受ける力強さがあった。事実彼らは風景を確実に背負ってしまえるだけの身体の強度を具えていたのである。
'93年より再び小空間に立てこもって新たな作業を開始したが、ここでもまた若い女優を中心に独特の集団的な演技が蓄積されていった。彼らの演技は名優が演じる芝居ではなく、演技はほとんど労働と見まがうばかりで、何かに扮する虚構の演技とはまったく異なったものである。例えば、天井に巨大な鉄の輪っかを付設するシーンでは、俳優自身が脚立に乗り、かなりの重量の鉄を支えながら実に折り目正しく取り付けに専心するのである。その姿は俳優というよりも工場労働者のそれに近く、劇場に労働を持ち込んだ感すらある。ちょうどアトリエの空間には鉄の階段が残存していて、装置の壁を取り外すと工場の趣が露出するようにもなっている。演劇がそのまま労働の観念と結びついている。わたしはこの〈本郷DOK〉を生産工場(ファクトリー)と呼びたい衝動にかられた。そういう観点から見ると、空間は劇場的な匂いというより廃工場のようであり、むしろジャンクアートの美術館の肌ざわりさえ感じられるのである。三つの舞台は、それぞれまったく異なった空間を造形して上演された。空間と身体が余剰にものがそぎ落とされた〈場〉のなかで思考される。
演劇が持続的な集団作業に裏打ちされた独自の表現〈文体〉をもつことを教えてくれる希有な集団が、この解体社なのである。
テアトロ 1994年/9月号