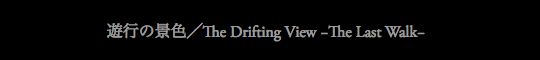世界を放浪する異形の群れがピエドモントパークに現れアトランタの風景を不気味に変貌させる
ー解体社 アメリカ南部を行くー
鴻 英良
遊行の景色
ピエドモントパークの池ぞいに無数のブースが建てられ、そこには美術工芸品がところせましと並べられていた。日差しの照り付ける9月、人びとは公園に繰り出し、品定めをしながら時折、感嘆の声を張り上げていた。展示品が織りなす一見カオスのような無数の色彩の瀑布は、きらきらと輝き、光沢を変えては、飛沫をあげながら、人びとに襲いかかっていたが、あまりの人の多さに、その瀑布のながれは、しばしば押しとどめられているようでもあった。ときどき上がる喚声の聞こえる方に歩いていくと、そこでは大道芸人が高い梯子の上で火のついたステッキを使ってジャグリングをしたりしている。
日本の前衛劇団「解体社」が "アート・フェスティバル" で公演をするというので、はるばるアメリカ南部の都市アトランタまでやってきたのだが、そこはまるで縁日のようであり、そこで繰り広げられている光景は、ぼくが知っている芸術祭や演劇祭のイメージとは著しくちがうのだった。解体社は本当にここで彼らのややフェミニズム的な作品「遊行の景色~」を上演することになるのだろうか。
しかし、公演のバスハウスやパビリオンのなかに足を一歩踏み入れてみると、そこには恐ろしく奇妙な物体が置かれていて、そうした物体がぼくの不安を取り払ってくれた。いや、そうした建物のなかに出現していた前衛性は、このフェスティバルがわれわれの知っているフェスティバルとはちがったコンセプトのもとにやられているのだということを明瞭に告げていた。たとえば、その建物のなかでは、電気椅子のようなオブジェが訪れた人にそれに座るように誘っていた。がらくたのオブジェが散乱していた場所の一角で、天井から吊りさがった ヘッドホンをつけてみると、暴行現場の悲鳴や暴漢の興奮した声が聞こえてきた。こうした作品がアメリカ社会の内部に巣くっている暴力の問題を扱っているということは一目瞭然だった。作品自体、迫力のあるものだったが、抜けるような青空の下で繰り広げられる明るく祝祭的な華やぎを脅かすかのように、こうした作品が展示されているというその置かれ方に、ぼくはひどく興味を覚えた。
これじゃあ、まるで、「ツインピークス」の世界だ、と思わずぼくは呟いていた。そして、解体社もまた、こうした縁日の華やぎのなかで、これらの前衛的な美術作品のように、ひとつの異物として現れることが期待されているのではないのかと思った。
現実の風景が異相に
ぼくは見晴らしのいい緑の丘に観客とともに座っていた。やがて遠くの方からまるで下着みたいな白い服をつけた女たちがやってきた。こうして解体社のアトランタ・バージョン「遊行の景色ー犬たち」がはじまる。そして橋のところにたどりつくと、彼女たちはそこで手を差し伸べたり、あるいは体を捩ったりしている。まるでどこかに脱出しようとしているかのように。だが、同時に、脱出は不可能であるかのように、彼女たちは前進したり後退したりするばかりだ。ほとんどむなしく繰り返される彼女たちの行為をぼくはぼんやりと眺めていた。大空の下で力を振り絞ろうとしている女たちの姿を見ながら、ギリシャの壺絵に描かれたミューズたちを思い浮かべ、ぼくはまどろんでいたのである。だが、やがて、彼女たちの遙か向こうに、黒い衣装の男がひとりじっと佇んでいるのにぼくは気づいた。なにをしているのだろう。ぼくは事の重大さにまだ気づいていなかった。だが、その直後、ぼくはこの男の存在にたじろかないわけにはいかなかった。彼が彼女たちを監視しているのはあきらかだったからである。そしてもっとも激しく踊っていた女が倒れたとき、その男が近づいてきて、彼女を背負って歩きはじめる。
ひとつの風景のなかにこうした人びとの姿を見ながら、ぼくはこのような物語をかってに作り出していった。だが、そうした物語を取り囲む自然の風景もまた見るものの想像力を刺激しないわけにはいかない。アトランタ・ジャーナル紙の演劇記者ダン・ハルバートは書いている。「劇のなかの出来事を取り囲むフレーム全体が、ー空や風、遠くから聞こえてくる音楽などー、演技をしていた。公園の向こうの通りを自動車が、音もなく、スローモーションで、不気味に滑っていくことに、人びとはこのときはじめて気づいたのではないだろうか」
公園のなかのスロープに解体社の役者たちが現れることによって、現実の風景が、別の位相のもとに現れてくる。こうして、アトランタの住人が、公園の向こうに、不気味なものを感じ取る。解体社の役者たちは世界そのものを異化したのだ。
だが、その日、解体社の役者たちはそれ以上のことはできなかった。はじめての場所で事態をすべて掌握するのはそれほど簡単ではないのだ。彼らはその後、観客に意味を伝えようとして失敗する。辛い一夜が過ぎた後で、翌日、彼らは意味を直接的に伝えようとすることを断念していた。だが、奇妙なことに、断念したとき、舞台はさらに多くのものを語りはじめたのである。そしてやがてアメリカの観客たちからつぎのような感想を聞くことになるのだった。「ここには虐げられた女性たちの反抗する姿が描かれているのでないか。そうした行為のもつ力づよさをわたしは感じた」
ぼくはこの劇の初演を日本で見たとき、「サイボーグ・フェミニズム」ということばを思い出した。それは屹立する女性たちのアメリカ的なイメージを表すことばだ。アメリカの観客たちはそれをこの舞台から感じとったのだ。
これは解体社の役者たちにとって、新しい反応である。それが彼らの舞台になにを付け加えることになるのか。そのことが海外公演を終えたいま、解体社の人びとに問われているのだろう。
毎日グラフ 1993年 11月28日号