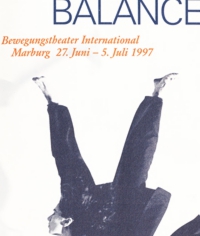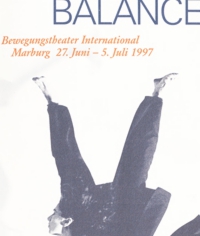この日本人のグループは「バランス・フェスティバル」で混乱と動揺を巻き起こした
解体社は暴力に満ちた舞台を観客に突きつけた
ピンターレンダー・アンツアイガー紙 (3/Jul.1997)
[マールブルグ発]劇団解体社の『東京ゲットー/オルギア』は、観客の試練を課すことをもってはじまった。一人の男優がじっと坐ったままの女の背中を、なんどもなんども、力一杯、平手でたたきつづけた。十数分のあいだ、平手打ちの高い音だけが会場に鳴りひびき、観客の動揺が徐々に高まっていった。女のむきだしの肉体はしだいに赤味を帯び、やがて、女の脚にむかって同じ野蛮な仕打ちがくりかえされた。
「ベオグラード(訳注:ザグレブ)の公演では、この場面を見て一人の男が舞台に飛びこみ、たたく男を女から引き離したのです。」と、公演後のアフタートークで劇団の主催者・清水信臣は語った。マールブルグにおいても、単調で無意味な暴力行為は、観客を同じような極度の緊張状態へと追いこんだ。
あとにくる演技も心優しい人には受けいれがたいものであった。役者たちは、意味のよくわからない、超現実の、神経を逆なでするような場面をつぎつぎと展開した。動作はゆがめ、ねじまげられ、声はとがり、音楽は野蛮な攻撃をしかけてくる。難解な暴力行為に満ちあふれた黙示録ふうの地獄が提示されるが、そうした絶望的な状況をもたらした原因はあきらかにされないのだ。よそよそしい大都市の情景、つらい旅を続ける人間たちの映像、無言の叫びを発する□と腕、そこからさらさらと流れおちる土くれ——そうした映像が、まるで狂気の画家の夢想を見ているかのようにくりひろげられるのだ。
生きながら死の硬直にとらえられた人のように、役者たちは生気のない仮面さながらの顔つきで舞台の上をさまよい歩く。幾分か緊張のゆるんだ動きをする唯一の存在が白いモルモットで、終幕近く、俳優たちの去った舞台をモルモットだけが動いている。
「わたしのおもなねらいは〈反暴力〉の表現にあって、逆説的ではあるが、それは暴力の表現を通じてしか可能ではないのです。」アフタートークに出席した数多くの観客にむかって、清水はそう語った。多くの観客が作品をどう解釈すべきかとまどい、具体的な説明を期待して集会に出てきたもののようだった。「わたしのなかにあって、いろんな場合にうまく処理のできない暴力を、いかに統御すべきか」——清水によると、それもまた『東京ゲットー/オルギア』のテーマの一つであるという。観客を混乱に陥れることにかれは意識的に賭けたのであって、賭けはマールブルグでもまちがいなく成功したといえるだろう。
日本人のもちこんだこの運動劇は、「美しい」作品とはほど遠く、ときには忍耐の限界に挑むようなところもあるが、脳裏に刻みこまれたイメージが感情と知性に長く訴えかげるもののあることもたしかである。