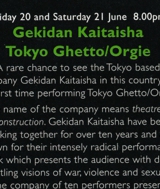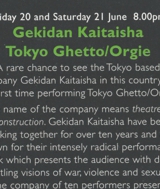脱構築工事現場の過酷な労働
Christopher Cook
スタジオの後ろでは、一組のテレビ・モニターが明滅する。椅子には、白い衣装を着ただけの女性が座る。不格好だが現代的な感じのする黒いビジネス・スーツに身を包んだ男性が足を引きずって歩き、この女性の背中を手の平で叩き始める。この人間トムトム(訳注、インド・アフリカなどで使う太鼓のこと)は穏やかなリズムで始まる。しかし女性の背中の皮膚の下には血が赤く浮かび上がる。そして明らかな恐怖の戦慄が観客にも浮かび始め、それはスーツの男性が彼のパートナーの正面を我々に向け、彼女をリズミカルに再び叩き始めるとき、最高潮に達する。このショウが終わるとき誰かがつぶやくだろ。これは我々が劇場で見た中で最もショッキングなものだ。マーロウのエドーワード2世の死よりも不愉快で、リア王のグロスターの失明よりも残酷だ、と。
しかし、もし残酷、つまり人間による人間の男女に対する非人間性がこの東京を基盤とするカンパニーである劇団解体社において、再帰的なテーマとして扱われているならば、我々は、60年代の前衛に愛された「残酷の演劇」から良き道筋をたどってきたということになるだろう。
『トーキョー・ゲットー/オルギア』(この作品は既にカーディフとグラスゴーで上演されている)のブリストルのアーノルフィニ・アーツセンターでの最初の上演の前に、劇団解体社の創設者であり演出家でもある清水信臣と話す機会を得た。それによれば以下のことが明らかになるだろう。つまり、このカンパニーが何度も試演されたテクストである「死の演劇」に取り組んでいること、あるいはアンドリュー・ロイド・ウエパー(訳注、ミュージカルの創設者)が、なぜ彼らをパックに詰め込んで東京から遥か彼方に送り出すのかということである(訳注、ミュージカルを愛好するような層が大半の東京から、追い出されたというような意味だろう)。このカンパニーの名前を訳して見れば、よく分かるだろう。「カイタイ」は脱構築を意味し「シャ」はカンパニーを意味する。そう「脱構築のカンパニー」なのである。
その上演において、劇団解体杜は非常に現代的かつポストモダンである。しかしそれはこの名前が提出する問題が緊急を要さないということを意味しない。むしろ、進展する経済にあって文化の領域における表象の危機とはいったい何なのか?あるいは上演ということで我々は何を意味しているのか?そしてアートにおいて「新しさ」という考え方が、なぜこれほどまでに文化的な誘惑力と蠱惑力を持つのか?清水は次のように客える。「私が新しいピースについて語るとき、それは新しいテクストや登場人物を意味しません。今日のアートのほとんどにとって『新しさ』は意味を為さないと私は恩います。我々はこのツアーで『トーキョー・ゲットー/オルギア』をグラスゴーとカーデイフのチヤプターセンターで上演してきました。そして今、ここブリストルにいます。ですからこの上演はほとんど新しい作品だと言うことが出来るのです。なぜならそれは我々が過去に上演したものとは違うのですから。どの空間にも差異があるのです。」
それでは観客もまた違うのだろうか?私は自分のサイズにあうポストモダンの帽子を被ろうと試みる。「ということは、三点のそれぞれに空間と観客、あなたのカンパニーを置いた三角形に、実際の上演は位置づけられるという訳ですね」。しかしながら、ああ、その帽子は完全にはサイズが合わず、私は図を描く羽目になる。清水はうなずく。(彼は生真面目な男性であり、もちろん黒い服を着て皮の帽子を目深に被っていた。そして眼鏡をかけていたがそれはラスコーリニコフが間違ってジオルジョ・アルマー二のブティックに入り込んでしまっていたら、選んでいたかもしれない様なものだった。)「その三つの関係は様々な側面により影響されます。社会状況がそうであるように。まず最初にピースが構築されます。それから上演の様々な要素により脱構築されます。そして脱構築された後、再び組み立てられるのです。つまり、構築、脱構築、再構築の繰り返しなのです。」
ビル工事現場のイメージが私に押し寄せてくる。煉瓦の入ったホッド(訳注、煉瓦、漆喰なとを担いで運ぶための柄の付いた箱)を運ぶ出演者。全員が被る保安帽。背景に流し込まれるコンクリート。最後に清水は彼の十人の俳優達について語ってくれた。「我々の上演は演技というよりはむしろ労働のようなものになるでしょう。それも強制された、より過酷なものに。」彼は能や歌舞伎の伝統的なトレーニングにも油断なく気を配る。そしてそこには、すでに終わった作業である舞踏のほのめかし以上のものがあった。
しかしながらスタジオではまだほとんど何も始まっていなかった。オープニングのシーンの衝撃のあと、演技の様式は優美さを持ったものになる。良く考え抜かれ、かつ精密さもある。そして、注目に値する持久力を持ったイメージが創り出されるのだ。ビデオ・スクリーンが戦争と平和、ハイキックをしている合唱団の少女達に対する儀式的な斬首、芸者のイメージをシャツフルしている間、登場人物の内の二人が包帯を巻いている。後ろにいる黒いマスクをした男は女性を身体検査している。シーンが一片の会話もなく進行するにつれ、他の三人の女性−一人は腰まで裸である−が椅子に彫像の様に座る。演劇の工事現場としての身体に関する理論的な議論は、これらの喉を切り裂かれた世界のイメージによって、わきに押しのけられる。
清水が語った様に「この作品のテーマは、この戦争と難民の時代に、どの様な権力が人間の身体を包囲し収監しているのかという問題に焦点が当てられている。」そしてジェンダーという困難な問題もまた「新たな奴隷制が進行する後期資本主義という状況において」浮上しているのである。
清水信臣との対話と彼の作業に関するレトリックは他人を寄せ付けないものではない。彼が語るところによれば、我々は古い政治的なフロンティアがどこかへ行ってしまった時代に生きている。共産主義の崩壊とベルリンの壁の崩壊は「新たな境界の設置を促しました。そして、それはナショナリズムの復活をも意味しているのです(劇団解体社は昨年ヨーロッパでの初の公演を、ザグレブの前衛演劇祭でおこなった。ザグレブはクロアチアの首都であり、そこでは人々はナショナリズムと新たな境界ということを分かっているのだ。)演劇の問題として考えるならば、私は次のことを重要な問題だと考えています。それは我々の内的な自己と外側の世界を切り離す図式です。かっては内側と外側にははっきりした境界がありました。しかし、今やその境界はなくなってしまっているのです。」
我々は再び身体、そしてアーノルフィニ・スタジオの天井から降りてきた巨大な輪で器械体操を演じる身体、に話題を戻す。座席の前の列に清水は座り、視線の力によって演技を演出しているかの如く前へ身を乗り出していた。俳優達は彼のために演じているのだろうか、それとも我々のために演じているのだろうか?人形遣いと動いている人形ということでこの関係を了解することができるだろう。そう、劇団解体社は清水信臣なのだ。
上演が始まる前に我々は会い、私は彼がどのようにしてそれぞれのピースを作ったのか尋ねた。「最初にテクストを書くということを私はしません。始まりは非常に独特なものです。混沌としたのものに見えるかもしれません。10人のパフォーマーは毎晩稽古し、そして私はそれぞれの人物達に特有の特性を見いだすのです。我々は写真や映画、演劇について話します。そしてこういったプロセスを通じて、私はその人物ために特別にテクストを書くか、あるいはイメージを提示するのです。これが始まりです。俳優によって私が驚かされ、取り付かれ、魅了される多くの瞬間があり、私はその驚くべき俳優の特性を舞台で上演することによって明らかにしたいと望んでいるのです。しかしそれは『日常の』ジェスチュアーなのです。ですから、私は家に帰るとその『日常の』ジェスチェアーを如何にして演劇に変化させるか考えるのです。」
アーノルフィニ・シアターでは、女性が一列になって—夢のなかにいるように、また包帯で手当されたかのように———ゆっくりと上演エリアを歩く。その一人は大きな丸々一つのキャベツを持っている。そしてここで、「トーキョー・ゲットー/オルギア」はある種の映画のように長くゆっくりとしたフェードアウトをそれぞれ異なる演技の部分の中で開始する。ガラスに入ったモルモットはどこから来たのか?。なぜあの女性はキャベツを歯で噛みちぎるのか?動物にあげるため?そして、スタジオの後の大きなスクリーンに映し出されるメッセージの本当の意味は何なのか?レイシストがやってくるのか?ここで古くて快適なアイデアに手を伸ばすことができるだろう。T・S・エリオットの「荒地」からの引用である。「我が荒地に引き上げたこれらの断片」。あるいはポストモダニズムは「引用の美学」として最も的確に表現され得る。
我々が劇団解体社の美学—このカンパニーは今年で十年になる—について語っていると、清水は小さな黒いノートを取り出した。最初はただの四角いノートに見えたが、その中にはたくさんの書き込みがあった。上演は8時前に始まることになっていた。もちろん彼は既に上演の概略を作っていなければならない。「懸命に考えているシーンが一つあるのです。最後のシーンの手前のシーンです。難民達の集団がステージに現れます。彼らの前には分割つまり境界を示すラインがあるのですが、私は難民達がラインを踏み越えられるかどうか思案しているのです。」
上演では境界は保たれる。20世紀のディアスポラのイコン、使い古したスーツケースと共に難民達は一方に側に留まるのだ。ぞくぞくするような演技。難民の一人が最初の場面で叩かれていた女性であることに気づく。今、彼女を叩いた加害者が近づき、彼女は彼を抱擁する。彼は笑う。平和になっていたのか?そうではない。なぜなら、彼は顔面を平手打ちされるからだ。もしこれがアーノルフィニの夏の一夜に向けて再構成されたものならば、偉大な演劇の力を形作るものとなるだろう。
大半の演出家ならここで上演を終わらせてしまったかもしれない。しかし清水信臣はさらに遠くへ進む。二人の俳優がしめくくりに登場し、男性の肩に女性が乗るのだ。後ろのスクリーンには、都市の風景、ストーンスローイング(石を投げつける)、そして最後のタイトルが表示される、クリスタルナハト・イン・トーキョー。真の終わりではないが、知的な感情的な始まりだ。ナチス・ドイツによるユダヤ人の迫害が60年の時を経て、どのように日本の首都に移動してきたのか?「構築、脱構築、再構築」そして解体社。今、答えはない。ただ不動のカルチュラル・フロンティアの周囲で意味を移動させること以外には。
Insight Japan誌 (3/Jul.1997)