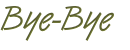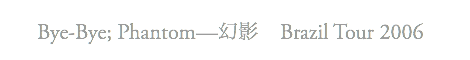「身体の演劇」を通して
清水信臣
三月、私は、公演のためにブラジルのサルバドールを訪れていた。リハーサルの合間に旧市街を散策していると、通りに面した家の壁に垂れ下がる一本の鎖に目がとまった。鎖は、がっしりとその先端を壁面に埋め込み、錆びついてはいるがなお太く頑丈である。その傍らで、パトロール任務の黒人兵士たちが、自動小銃をかかえて立っていた。かつては奴隷貿易の一大拠点として「繁栄」し、いまはそれらの遺跡を、たとえば、奴隷売買の市場跡や「水牢」という名の監獄などを、見物にやってくる観光客の安全のために、彼らはその目を光らせている。
この鎖は、この家の主人が、市場で買ってきた奴隷を軒先に繋いでいた鎖である。私は、もう長いこと「引き籠もり」、老いて死んでゆく飼い犬を抱きしめながら「この犬は、僕だ。」と話してくれた年少の甥を思い起こす。
ところでこの数年来、私は「身体の演劇」を標榜している。その理論的な事柄については別のところで書いたり話したりしているので、ここではその理念についてごく簡潔に述べたい。
「身体の演劇」が言おうとするのは、まずなによりも、「身体」は、実体ではなく「幻影」であるということだ。そしてこの「幻影=身体」は、あなたと、私のあいだにつねに在って、絶えず暴力の発動を抑止する制御機能をもった存在である。さらに「幻影」は、身体が、歴史的、文化的に造られたものであることを上演において露呈させる。経験上、このことは、とくに海外のパフォーマーとコラボレーションを行うときに、より鮮明に現れる。たとえば、上演において使用する母国語の問題を例にとれば、普段は英語を使うスペイン出身のパフォーマーがスペイン語で台詞を発語すれば、彼の身体は、当然のように、生き生きとした強さを持ち始めるだろう。だが、彼がメキシコのパフォーマーと向き合ったときにはどうだろうか、私の知る限り、その歴史的関係は、彼の発話形態と身体に決定的な「変化」をもたらす。それは、オランダの植民地支配を告発しているインドネシアの俳優と、そのインドネシア軍の虐殺を非難する東ティモールの活動家との対話のさなかにも、あるいはまた、自国の文化の豊かさを教えてくれたパレスチナのダンサーが、自分の家で家政婦として雇っているフィリピンの女性に接するときの、彼女の身振りのうちにも、そのような「変化」はもたらされる。すなわち「幻影」は、一切のナルシシズムを退けながら、身体を、「反省的思考」を欲望させる主体へと導くのである。
我々は「人間」じゃない。我々は日本人だ・・・出ていけ! 帰れ! 自分自身の土地へー (1)
一方で、「身体の演劇」に纏わるこうした作業は、その過程で深刻な軋轢を現場に強いてくる時もある。信頼するパフォーマーとの決別—その辛い夜に自問する言葉はいつも同じだ。「なぜ、国を背負ったり、背負わせたりしてしまうのか、それは政治が為すべきことであって、身体表現を志すものの役割ではない。それにいったい、そのような作業を強いる資格や権利がお前にあるのか、演劇に名を借りた搾取ではないのか」。なにより問われるべき対象は、演出をしているこの私である。応答しなければならない。
周知のように、俳優であれ、パフォーマーであれ、自分の身体を使って表現行為をするものは、すべからく身体知覚の延長を探求している。もともとは分離していたはずの知性と感覚の領域を、イメージによって(己の身体へと)融合させていくのである。この探求を、フィクションにすぎないといって冷笑することは私にはできない。それは、選択不可能な生存の条件に従って生きた、諸個人の生活史のなかに切実な根拠を持っているからである。生活史は、つねに(たとえば近親の)死者のまなざしとともに歩み、死者の身振りとともに、生ある身体に刻まれるのである。けれど、この原理は、民族と国家を想像力で繋いでいく、近代国家のそれとまったく同一なのであって、さらにまた国史が生活史の延長として機能するとき、それを読むものは、死者の、さらにいえば戦死者の声や身振り、表情さえも想起することができるのである。たとえばエシューとよばれるシャーマンが、奴隷たちの霊を身体に降霊させて、それらを祀り上げる「ウンバンダ」(2)の儀礼もそれであろう。それらをたんに共同体的なものとして片付けてしまうならば、あとは原理主義的なものを出現させるほかない。
しかしあくまでも「身体の演劇」は、ナルシシズムを退けてナショナリズムを批判する。それは、(上演において)それへの批判を言うことではあり得ない。そうではなく、身体が、ナショナリズムを露呈してしまうのは避けられない、まさにそのことを、つまりその事態の不可避性を、身体は露呈するのだということ。この事実を認めずに、「身体=幻影」を見ることは不可能のように思われる。
他方、「身体の演劇」は、「他者」の先行性をその本性とするがゆえに、その絶対的な受動性において「無力」である。生前、土方巽が語ってくれた、あの「剥製」のように。けれども、もし我々が、我々自身の「劇現場」に、あるいはかつて、それを育んでくれた日本の「前衛演劇」の先達たちと観客に対し、未来への責任を幾ばくか感じるならば、いまこそ「受動性」と「無力」において「運動」を語らなければならない時だろう。
我々は、この国の演劇がそもそもの始まりから無力であったことを知っている。すなわちこの国は、天皇制ファシズムが文化イデオロギー装置として絶対的に機能していた(る)がゆえに、とりたてて他の文化装置を必要としなかったことー我々は、こうした議論も理解しているし、それへの対抗の論理の構築を考えてはいるが、それと同時に、いま、ここで我々が直面している危機についても思考を巡らせねばならない。それは、グローバリゼーションと呼ばれる狂気の神話世界が、そのまま内面化されたような、新たな人間存在についての考察である。実際、現場でそのような「犠牲者」と直に向き合うとき、私は、ほとんど応接の不可能性に直面し、為す術もなく無力感に苛まれるばかりである。「幻影」のいない「劇現場」など、たんに悪夢である。
-----------------
(1)劇団解体社公演「制御系—anti-narcissism-」(2005/2月)の上演テクストから
(2)アフリカ土着の呪術信仰とカソリックが融合したブラジルの「新宗教」。
筆者は、その峻厳にして放埒な儀礼の「上演」をフォルタレーザ(セアラ州)で見る。
※この文章は「シアターアーツ」27(2006年夏)号に寄稿したものです。