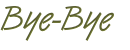此所を動かすのは誰か—
劇団解体社、最新作。ヨーロッパでの上演をへて、日本凱旋。
一切の美学的なるものとの決別を企図した「バイバイ」シリーズは、それゆえ演劇表象の限界を露呈しながらも、「グローバル化された戦争身体」を訊問に付していく「身体の演劇」である。舞台は1999年の初演から今日まで、「退化の世紀へ」「未開へ」「幻影」などと名付けた副題とともに、ヨーロッパ、アジア、アメリカ、ブラジルなど12カ国21都市をめぐり、そして今回「リフレクション」という名で東京に帰ってきた。
対談: 清水信臣 × 鴻 英良
Why "Bye-Bye"
鴻 昨年(2007年)の11月の末から12月の初めにかけて解体社は『バイバイ-リフレクション-』(以下、B-R)という作品をロンドンの「リバーサイドスタジオ」で上演したわけですが、それを今回東京でも上演する。そこで最近の清水さんと解体社の活動についていろいろ質問していこうというわけです。実はその公演に合わせる形で私もロンドンにいたわけですが、私は公演の後に解体社の日本の現代演劇における位置について喋らせてもらったのですね。それ以外にも2回、ポストパフォーマンスディスカッションというのを僕と清水さんとやったわけです。そこでいろんなことをしゃべりましたね。その後で解体社の何人かの人たちはポーランドのグダニスクに移動し、僕はそのまま、東京へ帰ってきたわけです。
いずれこのロンドン公演についての私の感想を喋るにしても、まず清水さんの考え方とかコンセプトを喋ってもらおうかなということなんですが、ひとつだけ最初に聞いちゃうとグダニスクのプロジェクトとこのロンドンの「B-R」とには何か関連があるんですか。かなり密接なつながりがあるものなのか、それとも比較的違うプロジェクトだと考えた方がいいのか。
清水 まず、この『バイバイ』シリーズですが、99年に立ち上げた時から「文字通り一切の美学的なるものと決別をしていくという上演」をコンセプトにしながらやってきたわけです。つまり美学的な関心だけでは応答不能な社会的政治的な事柄や問題系と、いかにして演劇が、あるいは「身体」が繋がっていけるか、ということですね。その後、世界各地をツアーして10年近くたつわけですが、今も『バイバイ』の方は、あくまで上演における表象の形式を問い返しながらその革新なり更新が企図されている。
他方、「夢」の体制-『ドリーム・レジーム・プロジェクト』(以下DRプロジェクト)の方は、たとえば今度グダニスクでおこなったことといえば、まずその当地にレジデンス(滞在)して、舞台作品を創っていくわけです、現地の人たちと。で、誰と創るかなんですが、今回は街の郊外にモナールというドラッグ中毒の人たちの更生施設があって、そこに暮らしている人たちで、だいたい20人ぐらい、14歳から25歳くらいの若い人たちと一緒に創ってですね、グダニスクの劇場で上演してきたのです。ここでは議論や稽古の方が、つまり(上演に至る)プロセスがとても大事です。まあ私としてはフィードバックというか、双方の作業から得た事柄が互いに往還することになるといいなと、そして演劇や身体の自明性をたえず揺さぶってくれるような思考の運動をここに求めてもいるわけです。
鴻 ああ、そうなんですか。今回のグダニスクはDRの一環だったんですね。私それを知らなくて、なるほど。
清水 そうですね.
鴻 以前、イギリス、ウエールズのカーディフでDRプロジェクトが始まったときにたまたま私はハンブルグにいた関係もあって、2回、前半と後半とワークショップに参加したんだけど。実際にDRプロジェクトの第1回というのはいろんな地域というか、いろんな場所からアーティストが参加していましたね。東チモールとかインドネシアとか、あと、どこでしたっけ、韓国とかアメリカ、カーディフ、ヨーロッパ各地とか。そういういろいろな問題を抱えているそれぞれの地域からいろんな人が集まってきて、グローバル化していく世界の中で表現者というのはどういう形でものをつくっていくべきなのか.自分たちの抱えている問題はそれぞれ違うかもしれないけど、それをどのように提示するのか、それについて何をするのかということを議論していくという、ある種対話的、論争的空間というようなものが、どのような形で舞台という表現に、繋がっていくかというプロセスを踏もうとしていたわけですよね。
そういう意味で演劇的な活動のひとつの形態としてね、非常に魅力的なある種のフォルムを清水さんたちは、作り出していったというふうに僕は思って見ていたんだけも。で、カーディフの後、確か東チモール、さらにヨルダン、そういういくつかの場所でも作業を続けて、今回グダニスクでもやられたと。今の話を聞くと、もう少し特定の問題を抱えた人達とその作業をやってみたということだから、ウエールズで僕が見たものと今回のグタニスクのものは必ずしも同じものではないように思いますけれども、いずれにしても東京に住んでいる我々が別な場所に行って、様々な人たちとグローバル化された世界における文化的な問題、あるいは生の問題、生きるということの問題をね、身体と言語を通して探求していくというやり方は、今回ロンドンで上演した『B-R』に繋がっていくわけですね。『B-R』はそいうひとつの舞台を見せるわけだけども、舞台の中にね、今言った反美学的、あるいは社会的政治的なわれわれの生の問題を、どういうふうに具体的な舞台作品にするのかということを考えるときの実践例だと思うのですが。じゃあ、どういうふうなコンセプトが『B-R』にはあるのでしょうか。
清水 ええ、もうちょっと『DRプロジェクト』の具体的な状況に踏み込みながら話をさせてもらうと、はじめに「(演劇が)いかにして繋がっていけるか」と言いましたが、今回のグダニスクでは「(演劇が)すでに繋がってしまっている」ことを問題化していく作業だったと言えるかもしれません。たとえば件の施設の更生プログラムですが、まず彼・彼女たちをレベル1から8までに分けていく、レベル8以上になるとその施設から出て行ける。この「カースト」はじつに徹底していて、最初の自己紹介のときなど、私たちにまず自分はレベルいくつかということを必ず言うので驚いたのですが、さらにそこではそのような管理のシステムに演劇も深く関わっているんですね。私は「治療」をおこなっているという演出家から話を聞きながら、演劇それ自体のもつ反動性にたいして、言い換えればディシプリンのための実践的なイデオロギーとしての演劇にたいして、つねに反省的であらねばならないと感じていたわけです。
あと鴻さんにも立ち会っていただいたカーディフでのことですが、あそこでインドネシアのパフォーマーと東チモールの活動家のあいだで、虐殺をめぐる和解不能とも思える対立が起こったわけですが、このような事態をどのように上演に繋げていけるか、そもそも私にそんな資格があるのかとか、ともかく表象をめぐる倫理について否応なく考えさせられたわけです。
いまも悩んでいますが、まずは自分の帰属する共同体が排除してきた出来事なり歴史にたいして、アーティストは自己批判的にというか反省的に関わるべきであって、ここからしか対話も始まらないんじゃないか。
鴻 たぶん今ふたつのことをいっていると思うのです。ひとつは「リフレクション」、つまり反省的になる、常に反省的に思索していくということ。もうひとつは「管理されていく身体」、バイオポリティックス(生政治)のただ中に我々が放り込まれている。少なくとも、どういうバイオポリティックスのなかで我々の身体が、どのような形で実際に管理されていて、それに対してどういうことが可能なのということを考えていかなければいけないということですね。つまりその「反省的な思索」が必要とされているわけだけど、その二つの問題を舞台で上演するときに実際に具体的にどうすればそれが演劇として可能なのか.という問題がDRプロジェクトの中でいろんな問題を含みつつ、少しずつ手探りながらも接近していくのが一方にあって、それを実際に『バイバイ』の上演の中でどうやって具体化していくのかということが問題になっているのだと思うのだけれども。今回のロンドンの公演において、極めて特徴的なのは、かなり大量の、少なくない量のテキストが舞台後方のスクリーンに映し出されていたということですね。いわゆる台詞劇ではないので台詞としての言葉を聞くということはあまりないのだけれども、テキストがずーっとスクリーンに映し出されていって、それを観客が読むことになるわけですね。で、一方、舞台ではパフォーマーの身体というものが存在しているわけだけど、そこには身体・動き・身振りというものがあるわけですよね。だから観客は舞台でのそうした身体表現というものを見つつ、かなり、集中するかたちでテキストを読んでいく。要するに観客にも思索を強いるわけです。で、とりわけ重要なテキストがたぶん二つあって、ひとつはコジェーヴの「歴史の終焉と人間の終焉」を巡るテキストで、もうひとつはアメリカの下院における「従軍慰安婦の決議案」。そのテキストを読みながら我々も考えなければならないにしても、それを選んできた演出家としてのモチーフはたぶんさっきからのグダニスクとつながっていると思うのですが。
肉体・身体・人体
清水 説明のために少し補助線を引かせてください。周知のように、90年代以降私はずうっと「身体の演劇」と言い続けているのですが、つまり「身体」がどのような状況になっているのかを演劇を通して考えてきたわけです。で、まず言えることはそれ(=身体)はきわめて歴史的なものであると。たとえば私が演劇を始めた70年代中頃まではこの「身体」というのは「肉体」と言われていたんです。それから、「身体」と呼ばれて。そして私は今「人体」と言い始めているのです。
ところで、60年代には「肉体」というのは“反乱”と一緒に語られていました。「肉体」が近代のヒエラルキーを転倒すると。つまり知性と感性というものがあったときに、その階層をひっくり返す、転倒していくのだと。革命のイメージと肉体の反乱はまさに同義語だったわけです。それが敗北したときに「身体」が登場したのだと私は思っています。「身体」—つまりこれは“生成的なもの”と“構築的なもの”が、いわばこれまで対立していたものが一体となっていくというか、“知性”と“感性”が一体化して“知覚”といわれるようになりましてね。例えればアポロン的なものとディオニュソス的なものがお互いに対立したり一体になったりしながら生成と構築を繰り返す、というイメージのなかで身体の可能性が、当時進展しつつあったメディア・テクノロジーとの共存とともに語られていたんですね。それで、今—9.11以降といってもいいですがー私が問題化している「人体」とは、アポロンーディオニュソスという概念で、この「肉体」なり「身体」を捉えるのではなくて、アガンベンなどが持ち出してきた「ゾーエー」のことであって、いまや「身体」は「ビオスーゾーエー」*(注1)という対で語られなければならないのではないかと、思ったんですね。で、この「人体=ゾーエー」というのはそもそも徹底して無抵抗で、いわば人間の身振りを忘却したような、ほとんど応接の不可能性的なようなものを身にまとった存在—私は「身体の要塞化」と呼んでいるのですが、その問題をやりたいということもあって今回「要塞化について」という副題をつけているわけですーそういった存在とどのように演劇が関われるのかということを、いま考えています。
鴻 そのためにコジェーヴのテキストが持ち出されてきたのでしょうけれど、コジェーヴが言っていることは「歴史が完了する、人間が終焉する」、我々がいうところの歴史的な意味での人間的なものが消滅して、消えていったら、人間の主体はどうなるのか、ということでしたね。
清水 あの辺りはですね、まさに「人体」を叙述している、それも「私的人体」と私は言っていますけどもそれをコジェーヴは「純粋状態におけるスノビスム」と名付けています。(註2) かつて(86年に)あの文章が日本に紹介された頃は、そのスノビスムの生が、つまり形式だけで生きていけたり死んだりできるっていうことが、たとえば「最後の人間」のイメージも含みながら、むしろ「豊かな」ものとして語られていたのを覚えています。ところが今読み返すとなぜか非常に物騒なものですね、ちょっと耐え難い。それはおそらくあれらの叙述がいまや現実となったからです、つまり彼が描き出したポストモダンな人間—「最後の人間」—「人体=ゾーエー」がまさに「グローバル化された身体」として世界中いたる所に出現しているという事態、この事態の「起源」を問い直したかったのであの文言を投写したわけです。
鴻 今や「肉体」でも「身体」でもなく、「人体」という使い方をすべきだということは非常に面白い考えだけど、一般的にそうしたことが歴史的な文脈の中で明瞭な形で問題化されたのは、ミシェル・フーコーの「監獄の誕生」の中でしたね。そこで問題になっていた公開処刑の話をちょっというと、公開処刑というのが19世紀の前半くらいにヨーロッパの各地で消えていって、その代わりに監獄が誕生した。その結果、人間の身体や精神に何が起こったのかを分析したのがこの本です。つまり以前、犯罪者は公開の場で体を痛めつけられ、引き裂かれ、そして華々しく散っていたわけですよね。そういう華々しい身体というものが、公開処刑の消滅後、監獄に監禁される。独房に監禁され閉じ込められ、そこで監視され、規律・訓練に晒されるといった形で、近代社会において肉体はいわば消滅に向かう。それで、そういう中で反乱としての肉体が模索されていたんですよね。そのプロセスの中で何がいわれているかというと、肉体が消滅していくという危機意識が人々の中に芽生えてきたとき肉体を回復しようという動きがダンスや演劇の中で起こったということですよね。それを肉体が置き去りにされるという言い方をすると、ゾーエーという段階において起こっていることっていうのは、肉体だけが置きざれにされているのではなく、最近になって言語も置き去りにされていたということがはっきりしてきたということなんですね。このことが最近了解されてきたと思うんだよね、肉体とともに理性とか言語とか反省的思索とか、そういうものが置き去りにされた状態を表わす言葉が人体なのですよ。だからたぶん今回の舞台で非常に重要だと僕は思ったのは、コジェーヴのテキストがそういう問題を考えさせるという契機としてね、観客によって真剣に読み込まれていく。舞台を見ながらね、そこが今度の作品の非常に大きな特徴だと思ったんですよね。
あと熊本さん(俳優)が読み上げている「戦陣訓」がありますよね。あれは彼がえらく深刻に読みあげていく、その姿を見ながら、この特異な言葉をわれわれは耳をそば立てて聞いてるわけですよね、あれも台詞ではないのだから、観客は何が言われているかを考えて聞く、つまりスクリーン上のテキスト、あるいは呟かれ読み上げられているテキスト、それを観客が思索しながら読み、聞くというそのプロセスの中で舞台を見ている。舞台には役者がいる訳ですからね、芝居をしている訳ですからね、そういう意味でいうと、いわゆるゾーエー化した人体のような存在としての人間が、その舞台上のパフォーマーとしてね、そういう言語との関係の中でどんなことを構想しているのかが問題になってきます。
ゾーエーこそが思考する
清水 たぶんに逆説的ですが、私はゾーエーこそが人間の思考を回復出来るのではないかと思いたいんです。たとえばですね、また先ほどのドラッグ厚生施設の話になるけど、稽古の時にこういうことがあったんですよ。つまり、彼らのうち何人かに、コンフェッション(告白)というか、自分の事を語らせてみたんです。まずそれを録音/録画して、舞台上に流す。と同時にリアルタイムでも発語してもらう、それを聞きながら同じ事を喋る、「二度性」というか、反復ですね。内容は辛いものです。十四、五の頃から麻薬に浸っていて、麻薬が買えなくなる恐怖にずっと怯えていて、その為に盗みをしたりして五年間刑務所にいてとか、まあそういったものです。とてもシリアスで聞いている方も皆しんとするわけですね。で、その中の一人の子がね、自分の番になるとなぜか大笑いしてこれが止まらないんですよ。何回やっても。周りに関係者もいましたから、「まじめにやれ」とか「もっと集中して」とか言い始めて、まあでも私は「いいんじゃないか」とも思ったんですね、たぶん彼の笑顔があんまり無邪気なんで納得してしまったというか、まあそれで、その時は何も言わなかったんです。で、アフタートークのときに仲間の一人が「稽古のときは笑っていたようだけどどうしたんだ」と尋ねていました。彼の応えでは「実はあの稽古のとき初めて自分の声を聞いた。それが、なんとしてもおかしかったと。奇妙で、どうしても納得できない、変だ、自分の声が、とてつもなくおかしいしそれを聞いている自分もさらにおかしい」。私はそれすごく重要だと彼にいったんですが、何がいいたいかというと、自分の声じゃないわけですよね。声って言うのは。あるいは自分の声でさえ、自分とは違うものだと、それだけ違和感がある中で、つまり、自己でないものをどのように、自己が受け入れる事が出来るか、そういうことに関わっているのではないかと。つまりこの問題というのは、ふだん一番近しいと思っていた自分の声でさえ、他人のものというか、ともかく自分ではない誰のものでもないのだという体験もしくは時間。彼は私たちが排除しているものに敏感だった。まあこの文脈でいえば、ゾーエーは我々が、ビオスの側が排除しようとしてきたものだと、で、いかにそれを再び迎え入れることができるか、その方途を知っているのもゾーエーではないか。
鴻 具体的に『バイバイ』の中でそういうものは例えば個別的ないくつかのシーンの中で、どういう風に展開されているのか。
清水 前半のムーブメントだけで構成されたシーンは「目的なき要塞」と名付けたのですが、まずゾーエーは目的のない世界を生かされているということ、そもそもグローバリゼーションには目的がないわけですね。で、なにがあるかというと、管理がある。で、管理は何をしているかというとひたすらビオスとの境界線を引きながら監視を行っている。いまやこの監視システムは(公共)空間を奪取して我々の生をいわば内的な時間を営む動植物のような存在へと追放していくわけですが、このシーンのムーブメントはそうした生の様態を描いています。
このような状況下で、後半の「裁きなき要塞」で扱っているのは近頃私たちの周囲で多発している殺人です。なんの理由もなく刺し殺すとか、あるいはよく「心の闇」とかで語られたりする犯罪者たち—実は彼らはグローバリゼーションが生みだしているのではないかと私は考えます。なぜかというとおそらく人間は目的のない世界を生きることができないからです。たとえば宅間守という元死刑囚がいましたよね、彼が裁判で語った言葉は、自らが神になるという目的です。「自分は殺した子供を選んだ。子供達は自分に選ばれたのだ。」と、そして「はやく死刑にしてくれ」というわけです。つまり生殺与奪権を握りそれを行使して、かつ国家に死刑(殺人)という罪を犯させることで法=秩序をも超越していくというような(神になる為の)戦略をもってそれを実行した人物ですね。「なにも見るな、信じろ」というテロリズムの思想とどこかで通底しているのかもしれない。いずれにせよそうした人物が出現してくることの意味を考えることは、演劇の問題なのだと思っています。
鴻 最初に主体を失った者が主体を剥奪されることによって、そこから主体を取り戻していく、再構成していく、そういう必要性、そういうシチュエーションの中に置かれたことがゾーエーであるということですよね。だからその、そういうのと今の宅間が自ら神になろうとすることによってね、あるいは死刑にしてもらうことによって、彼が初めて自分の存在を確認できるというような、そういうシチュエーションの中に我々が置かれているということですよね。だから、それはグローバル化の中で我々が象徴的機能を実は完全に剥奪されてしまっているという問題ですね。で、結局、脱主体化とかいうようなことを、ある種ユートピア的にというか、ユーフォリア(多幸感)的に考えていた人がたくさんいたわけですよね。しかし、実際に主体が崩壊していくというプロセスの中から行き場を失った人間がね、今言ったようなある種の超越的な領域へと犯罪という形式を通して入っていこうとする、そういう状態はやっぱり極めてまずいわけでね。だから何故そうなっていくかということを我々が考えなければならないんですよね。
清水 他ならぬ私たちが創り出しているのだということですね。
鴻 そのことを舞台の上で反復していくというか、繰り返して維持していくことが『バイバイ』という作品の、まず構造になっているということなんだけれども。ロンドンで一緒にいたから僕らはいろんなことを話合いましたが、ちょっと非常に興味深いなと思ったのは、コジェーヴのテキストをこれは、結構難しいなと思いながら二人で読み直していてね、あのときに新しい発見があったと思ったんですよね。清水さんはあの時ね、読んで何か言ってましたよね。あそこで最後の4行くらいがわからないという話から始まったんだけど。
収容所における主体の形成は可能か
清水 要するに何か極めてですね、有用なことも言ってるんです。この部分ですよね。「従って歴史の完了後も、なお人間性において留まっている為には、」と出てくるんですよね。
鴻 もうちょっと読んでくれますか。
清水 「人間は所与と誤謬に対する否定性としての行為が消滅した後にもなお、対象に対抗する主体であり続ける必要がある」(注2)ここは読み落としていたんですね。それで鴻さんとコジェーヴの問題をアフタートークやろうといったとき、まあちょっと読み落としていたんで、これを問題にしてみようと話し合ったんですよね。
鴻 この文章ではコジェーヴはいわゆる動物的という概念が持ち出されてくるとき、一般的に考えられているようなものは逆のことを言っているわけです。つまり、人間が人間的でなくなって動物化していく。その場合においてさえも主体は対象に対抗する主体でありつづける必要があると言っているわけですよね。これは一般的なコジェーヴ理解として日本で流通しているものと全く違うものであって、さっきゾーエーっていうものの中にその可能性を感じなくてはいけないいうふうに清水さんは言いましたが、それはゾーエーであることによって初めてね、その奪われた主体がふたたび、言ってみれば回復されるという、その可能性が出てくるんだという話と繋がるはずですよね。だからコジェーヴのその文章をね、何となく歴史が終わったっていう話で終えてしまうんでなくてね、可能性のテキストとして読むべきだと思うんですよ。コジェーヴはもはや歴史は終わっているって言ってるわけですよね。だから、これは未来の物話ではなく今の問いであって、コジェーヴは、常にこれを見よと言ってるわけですよね。で、実際にはアガンベンはそのたとえを例えば30年代の終わりから40年代のヨーロッパ、つまりアウシュヴィッツと関連づけている。アウシュヴィッツにおける人間の在り方を見れば、歴史は終わっているし、人間は終わったんだということが分かるというわけです。これが人間か、それこそプリーモ・レーヴィの言葉であるわけだけどもね。*(注3)
そしてアメリカとか日本とかいろいろなところに行く事によって新たな体験をするわけですが、そこから日本人の生の形式の中に、極度に動物化されたスノビズムとういうのがあるという話をしていて。だから主体から脱主体化へというようなヴィジョンを持ち出してきた人がたくさんいるけれども、そうではなくて、対象を否定する主体としての何かが、まあ残余が残らなければならないと、実はコジェーヴは言っている。それをいかに獲得いくかということが管理社会というか、収容所化された、清水さんは要塞と言っているけれども、そういう世界の中でね、人間が、にもかかわらず主体でありつづける為の、そういうその方法を見出さなければならないんだというようなことをね、コジェーヴのテキストを舞台の上で読みながらね、観客もまた考えているということが重要なことだと思うんですよね。
もっともコジェーヴの文章をアガンベンが分析していろいろ語っていますけれども、(注3)だから、「リフレクション」、「思索の場としての演劇」というものを構想するときに、このコジェーヴの文章を読み返す、再読するという作業自体が演劇の中核に入っていくということがね、ゾーエーの問題と、極めて密接に関わってくるということですよね。
清水 そうですね。
鴻 で、なんというか、身体知覚、人体感覚というか、その感覚のようななものと「演技」といわれるものとの間の関係というか、舞台をつくっている時の、構成している時のその身振りや動きというようなものについてどんなことを清水さんは考えているんだろうか?俳優・パフォーマーの具体的身振りと動きと、今まで語ってきたことのような、ある種人間が置かれた状況の中での人体の在り方みたいな、そういう問題とをどういうふうに繋げて実際に稽古したり、舞台でパフォーマーに動いてもらっているのか。
剥製、もしくは絶対的受動性
清水 様々な古今東西の重要な演出家達の文章や発言についてこのところ参照をしているんですが、とりわけ私にとって近しいというか重要なものはやはり土方巽の語っていることですね。よくね、土方のことを土着的身振りの回帰とか、「東北」へのノスタルジアとかそんな言葉でもって伝統の中に博物館化しようとする向きもありますが、私はそう思わなくて、むしろ彼の語ったことっていうのは今非常にアクチュアルなんじゃないかと。たとえば「剥製」とか「衰弱体」といっている。「剥製」というのはどういうことかというと、私の考えでは、要するに「見られる」、こう他人から見られたときにね、通常は見返すのですね。よく演技の指導なんかでも「はっきり相手の目を見てフォーカスしてしゃべれ」とか言われるわけですよ。だけど「剥製」は一切そういうものを無化してしまう。どういうことかというと、見返すのではなく映させるのだということ、この眼球の表面に映させる。いわば自分の体をスクリーンのように扱うというか、そういう概念ですね。これはもう絶対的な受動性に晒された身体、ある意味でゾーエーと言ってもいいような状態を名指しているようにも聞こえるわけです。
鴻 今度の『B-R』なんかのパフォーマーの身体の在り方というのはそういう方向を目指していると。
清水 そうですね。唯一見返すことができる存在は舞台に敷かれている、「鏡」だけなんです。ともかくまずはそういった剥製状態をつくりながら、管理のイデオロギーといかに拮抗していくのかを「Transformation(生成変化)」「Nervous System(神経系)」「Phantom Pain(幻影肢)」 「Repetition(反復)」といった概念でもって考えているんですけども。今回とりわけ重要なのは「反復」だと思いますけどね。まあ反復といっても様々な形式があって一つは(字義通り)単にくりかえすこと。それも、ひとつの言葉、ひとつのリズム、ひとつの快楽を繰り返し身体に刷り込むことで、迫力とか生のエネルギーとか呼ばれているものの回復が目指される。これは「身体」を「肉体」としてみているわけですね、フィジカリズムとでも呼ぶべきか、つまりフィジカルな能力の優劣でもって「身体」をみていくような視線の制度のなかでのみ機能する洗脳、プロパガンダ、そしてメディアイメージ—それらは一回性を装いながらたんに反復する。
二つ目は、こちらの方がより本質的だと思われるのですが、過去のトラウマ記憶が現在に蘇る。というか「反復」してくる。それらはときに歴史性を伴いながら、絶えず自らめがけて回帰してくる。
鴻 今清水さんが言っているのは「反復脅迫」というフロイトの概念のことですね。戦争性外傷、トラウマが絶え間なく繰り返し回帰しているということで、いわゆる普通の意味でのなんていうかリズムとしての反復ではないんですよね。まさに回帰してくるものとしての反復。
清水 通常のリズムとして処理されたものに関しては、「神経」を使う。神経の束がこう、知覚されてくわけですけども。それを使って潜在している「身振り」を動かすということですね。ちょっと言い方が変ですけど、そもそも自分の「身体」は他者の身振りの集積から創られているという考えですね。たとえば、私が先にあるのではなくて他が先にある。というような言い方を土方はするけれども、そこに彼が「舞踏性」と名付けた理念の根本があると思うんですね。私はしばしば引用しますけども彼の言葉に「この春先の泥から私が教わったことは、私の舞踏は断じて神社仏閣のものでは無い」(註4)とか言っている。つまり春先の泥のほうが私に先行してあるということ、この春先の泥という他者から私は教わるのだということ。そのような思考をしている限り、断じて、神社仏閣の、つまり国家や共同体が称揚するような、ナルシスティックな芸にはならないんだと、こういうふうに明言している訳ですから。あるいは「東北が東京に輸出するもの、それは兵隊と芸者と馬と米だ」(註5)といったきわめてポスト・コロニアル的な発言も念頭におきながら、土方と舞踏というものを「ビオス-ゾーエー」の対概念を参照しつつ、さらにアクチュアルに捉えていくという作業を継続していきたい。
鴻 その際、ゾーエーという存在の様式に関わろうとすることは、ひとつの侵犯、トランスグレッションの行為であって、それをラカンの言葉では「アーテー」と言うんですよね。要するに我々は普通は象徴界にて、ある領域の中で極端に走ったり、非常に衰弱していたり、中間的にいたりとかあるんだけども。ある領域、ある限界を実は越えることはあまりない。それを超えてしまうと、その瞬間社会の中に存在できなくなる。つまり社会の外側に人間存在として放擲されてしまう。それを「アーテーを超える」というんだけども。そういう存在っていうのは長く生きていけないと言ってるんですね。たとえば、アンティゴネーはクレオンの象徴界のシステムに対して、兄を埋葬してはならないという法があるわけですが、その法を破って兄を埋葬するわけね。彼女は夜陰にまみれて、明け方より少し前にそれをやるわけですね。だから暗闇で見つからないわけです。一回目はね。そうするとすぐに兵士たちが埋葬されている遺体をもう一度泥を払ってね、そして王の命令通り元へ戻すわけですね。そうすると今度、日が昇ってからもう一度かけに行くわけですね。つまり一回目はこれは普通の行為なんだね、二回目はこれはもう完全に逮捕されることを前提にして行ってるわけです。そして実際に兵士に拘束されて、そしてクレオンの前に引きずり出されてね、おまえがやったのか、いや私はやってませんとこう言えばね、いえやったろうとそういう話になるだけど、いえやりましたとアンティゴネーは言うわけです。この瞬間からアンティゴネーは象徴界の秩序から完全に逸脱すると、なんか宅間とちょっと似ているような気がしないでもないんだけどね。それを「アーテーを超える」と言う。だから彼女は基本的にその段階でもはや死の世界に入り込んできている。で、結局最終的に自殺することになるんだけど。要するに岩屋に閉じこめて餓死させるというのがクレオン側の判決だった。そういうような行為っていうようなものこそがね、Gestus(ゲストゥス)、身振りなんだ。つまり身振りっていうものは象徴界から脱落するそういう場所に実はあるんだとラカンなんかは言ってるわけですね。それを目的なき手段とアガンベンは言うわけです。さっき清水さんも目的のない世界って言ってたけども結局、それは行き場がないというあるシチュエーションというものが表現の根幹に実は横たわっていて、それとどう触れていくかっていうのはね、ある意味で否応のない形で現代の人間がね、グローバル化というその流れの中で投げ込まれている状況からくる問いなんですね。その中での主体というもののいわば獲得というね、パラドックスみたいなものが舞台だけに限らず、人間存在の在り方として露出してきている。だからそれを本を読みながら頭の中で考えているひともいるだろうし、舞台という実際の人体が登場する場所で、それを集団共同作業のなかで舞台としてつくるか、ワークショップというような形の中で展開するか、やりかたは違うけれども。そういうことを実践することの重要性が今日ますます出てきているわけです。『B-R』という作品は、非常に意識的にそういうことを追求している。そういう意味で今度の3月の作品に私は期待してるわけです。
(2008年1月27日/湯島 スペース・カンバスにて)
※この対談は『バイバイ;リフレクション』東京公演(@あうるすぽっと/3.6—9)のパンフレットに掲載されたものです。
_________
注1)
アガンベンは『ホモ・サケル』(以文社/高桑和巳訳)において、生(ヴィータ)という語でイタリア人が了解しているものをギリシア人が、ゾーエー(Zoe)とビオス(bios)に区別していることを重視した。「ゾーエーは、生きている全ての存在(動物であれ人間であれ、神であれ)に共通の、生きている、という単なる事実を表現していた。それに対してビオスは、それぞれの個体が集団に特有の生きる形式、生き方を指していた」と書いている。
注2)
アレクサンドル・コジェーヴ「歴史の完了についての二つのノート」(『GS・たのしい知識』vol.4、1986、所収、丹生谷貴志訳)
注3)
「これが人間か」(Se Questoe’ un Uomo)はプリーモ・レーヴィ『アウシュヴィッツは終わらない』(竹山博英訳、朝日選書)の原題。
註4) 土方巽
風だるま
舞踏懺悔録集成 舞踏フェスティバル85 前夜祭講演 衰弱体の採集より
現代誌手帖
1985年 所収
註5) 土方巽
舞踏フェスティバル85の公演会場、新宿文化センターロビーにての発言
1985年/2月18日
NHK衛星放送収録