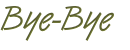into the century of degeneration
Peter Eckarsall
劇団解体社の『バイバイー退化の世紀へ』(1999年)は、この種の[訳者注:80年代と切断された90年代における、資本-戦争によって攻囲された身体性の]リアリティの探求を目論む作品だった。90年代を通じての解体社の一連のパフォーマンスと引き合わせてみると、この作品では、上記のとおりステファン・バーバーによってまことに適切に述べられていた「身体的苦闘」の感覚が表現されている。
切迫していながらも暗黙のうちにとどまる暴力の感覚が、展開された断片のように空気感のなかに漂う。パフォーマンスにおける不穏で挑発的な瞬間は、次のようなシーンにおいて現れる。ある女性は、表情を欠く工作員のような男性から次の男性へと、生気を喪って反復的に投げ渡される。また別のシーン――これは何度も反復されるものだ――では、まるで見知らぬあるいは失われてしまったいくつかの世界地図に駆り立てられでもするかのように、パフォーマーたちが広大で何もない舞台空間をさまようなかで、難民のごとき感覚が喚起される。彼らは羊の群れのように、あてもなくまた別の強さや軌道のもとで送り出されるためだけに集まっている。演劇批評家の西堂行人が示唆するように、清水は日本人の身体を「家畜身体」と考えているのだ(西堂、2004年)。
一方その間、他のパフォーマーたちは繰返し自分の大腿を叩き続けることで、直接の暴力的パフォーマンスを自身の肉体上で演じている。パフォーマーの包帯を巻かれた、傷ついた身体は、苦痛と喪失の強烈な感覚を喚起する。作品内のきわめつけのシーンでは、パフォーマーたちは突然に立ちすくまされ、微細で根源的な筋肉の痙攣のほかにはもはや動くことができなくなる。巨大な、ほとんど圧倒的ともよぶべき戦争の映像が舞台全面を覆う。ゼロ戦や、行進する日本兵の隊列や、戦闘の暴力のさなかにある身体といった映像群が、パフォーマーたちの機能不全となり外傷を負った身体を洗い流す。こうして彼らは、まるである種の軍事規律的な渦のようなものによって、消滅へと駆り立てられる。このシーンはパフォーマンスという固定化された観念を越え出ており、その強度は筆舌に尽くしがたい。とはいえ、溶解の感覚を刻印し、いかにしてその莫大さと痛みとによって1980年代の日本演劇の表象における美学を拒絶しているかということは明らかである。
空間、人種、監視の合成体が本作の終着点である。そこに至っては、空間における身体とその現前性を溶解する能力において舞台の基本的諸要素は出尽くしてしまっているため、もはやこの上どんな作為の余地もないかのようである。「解体(deconstruction)しかない」と清水は言う(解体社、2001年)。この言葉によって、なんの意図もなく空間に住みつく、これらの奪われた空虚な身体を説明することができるかもしれない。清水および彼の劇団にとって、これは象徴的あるいは演劇的な比喩ではなく、事物のあり方をただシンプルに表現したものである。彼の言うところでは、「身体は事物を明るみにもたらす」のだ(清水、1996年)。この「証言」の演劇によって、『バイバイー退化の世紀へ』はグローバル権力と帝国へと向かうイデオロギー上の変容および趨勢を証示しようとする(あるいはそれらを結論づける)。
"Gakidan Kaitaisha and The politics of bodies in angra" より一部転載