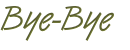残忍な力が道理を導く
Hilary Crampton
日本の劇団解体社のパフォーマンスは、甘い表現などは一切無く、とにかく暴力と荒涼としたシーンの連続だった。観客がおしゃべりしながらダンスハウスの厳粛な場内に入ると、彼らは戦時下の虐殺を映すフィルムに襲われたのだ。この残虐な映像を背景に、小さな女性の人影が空間の中をあてもなくさまよっている。しかし観客は最後に照明が消えて初めて、無駄なおしゃべりをやめたのだ。
このように、観客は目の前の出来事に自発的に集中しないという過ちを犯すのだが、これは常に合図に従って行動している私たちがそういう権力的な支配を受ける時に、いかに無自覚であるかということを示す象徴的なシーンだった。
「Bye-Bye」において、演出の清水信臣は日常のふるまいから表面的な飾りを剥ぎ取り、人が暴力を自分や他人に対して行使することに喜びをもって行い、そして応じる様子をまざまざと暴露する。パフォーマーたちは取り憑かれたように反復行動に従事する。それは権力のマントラを躁病患者のように叫び続けるシーンや、女性が自己破壊的に3人の男に身を投げ出し、暴力的に拒絶されるという行為に見て取れる。
ある男が自分の腿を腫れ上がるまで叩き、リズムを弾き出した。一方で半裸の弱々しい女性が震える足で前進し、くずれ、そして立ち上がるという行為を繰り返した。彼らがこのような自虐的な行為をしていない時は、それぞれが全く孤立しているように見える。お互いに孤独で、お互いの感情の交流が無いのだ。
象徴的な外見をした者たちもいる。顔に包帯を巻いた女たちだ。精神は効力を奪われ、肉体は壊れやすく、かりそめのものにされている、そんな女性たちだ。
爆弾による破壊や戦闘機が投影される映像を背景に、舞台が様々な表象で満たされるのと同時に、使われている衣裳もその者の社会的な役割を明確にしている。突然の静寂の中、ある一人が携帯電話でしゃべっているのが聞こえてくるまでは。このシーンは、破壊的な力が日常になっている現代の様子を象徴的に表していた。
最後に、腕に鎖をかけられた女が一人孤独に座っているところへ、抑圧と否定の呪文が我々の目の前で閃く——「感情を麻痺させよ、思想を検閲せよ」
解体社のパフォーマンスは力にあふれた演劇であり、心臓の弱い者にはお勧めできない。人間社会における権力の作用を探求するその演劇の中で、演出の清水は剥きだしの暴力と日常のありふれた出来事の間にある芝居に私たち観客を直面させる為に、彼自身の権力を我々に対して発揮してみせるのだ。
俳優たちは時に、作品の信頼性にとって重要視される自発性の感覚を失っているようにもみえるが、この芝居にどう猛に身を投げ出している。
THE AGE紙 メルボルン, オーストラリア (9/Dec. 1999)