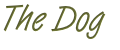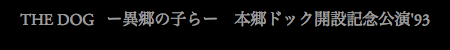かつては観客もまた歩いていた
ーひとつのパラドクスにエールを送ろうー
鴻 英良
解体社とともに、われわれは、ひとつの逆転につきあっていた。この劇団とともに、われわれは劇場の観客席に座って何者かが訪れてくるのを待つというやり方をやめたのである。いつからか、この劇団は観客席を放棄してしまっていたからだ。
確かに、彼らはやってきた。いつも、彼らは、まるで旅芸人のように、大きな鞄や荷物をもって、われわれのまえに姿を現した。われわれがそうした彼らを出迎えることができたのは、そのような彼らの出現の場所が、ひとまずはわれわれにも知らされていたからである。だが、彼らはすぐにどこかへ旅立とうとしていたのである。そして、彼らについて少しでも何かを知りたいと思ったならば、われわれ観客も、彼らの後を追って、旅立たなければならなかったのだ。
こうしてわれわれは、幾度か、"歩く観客" になった。"座る" から "歩く" へ。この変化は、われわれ観客の感覚と認識作用に決定的な影響を及ぼした。劇というものを歩きながら見ているという意識だけでも、われわれの感覚を根底から揺るがすのに十分だった。『遊行の景色』と題された彼らのシリーズは、概ね、野外のどこかを移動しながら演じられていたわけだが、役者が劇場のセットの中にではなく、現実の風景の中で演技をしているということでも、役者の演技や身体はちがったものにみえるし、そうした役者の存在によって、風景そのものがまた変わってみえてくる。いわばさまざまな異化がここでは実現しているわけだが、そうした異化が、"歩く" というわれわれ観客の行動で極度に増幅されたのである。
"歩く観客" とは、空間を浮遊している観客のことだ。その観客の存在形態自体が、無根拠性の中に観客をひきつれていった。そのことが時代精神を巧みにすくいとっていた。解体社のこの「移動演劇」はその意味できわめて現代的な劇形態であったのである。
俳優の身体感覚や劇の物語も当然そのことに影響された。俳優もまた浮遊しなければならず、中心化することを拒絶された劇構造は、解体へと向かう劇構造にならなければならなかった。つまり、解体社の劇はポストモダンにおける物語の終焉という物語に見合っていたのである。
そのようなとき、ぼくは、中心化することを拒絶した解体社の役者たちの身体から実体的なものが消えようとしていることに着目し、彼らの身体を "媒介としての身体" と名づけた。だが、いまにして思えば、彼らの身体は、どのようにして、なにとなにを媒介していたのか、われわれはもっと多くのことを考察しなければならなったのだ。しかし、どのようにして、それが可能なのか、その方法がなんであるのか見出せないまま、かなりの時間が流れた。
だが、解体社が、今回、都市の中心に密室的な拠点を作って新たな活動を開始しようとしているところをみると、解体社と演出家の清水信臣は、長い思索の果てに、そのような作業を、密室的な空間で、いわば思考実験のやり方を擬しながら押し進めてはどうだろうか、と考えはじめたように思える。
ふたたび密室へ。この興味深い逆転が現実に何を生み出すことになるのか、ぼくはまだ知らない。だが、これが少なくともひとつの回帰であることはまちがいないし、それが単なる回帰でないにしても、彼らはひとつの逆説(パラドクス)を選択したことは確かなのだ。解体社に興味を抱いてきたわれわれは、これからひとつの逆説(パラドクス)につきあうことになるのである。
(公演チラシより)