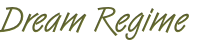劇評・『夢の体制』
デヴィッド・アダムス
2004年1月30日 『ザ・ウェスタン・メール』
カーディフ、ウェールズ、英国
予報されていた寒波がやってきたという刻に、日本のカンパニー「劇団解体社」がパフォーマンスの前半の二つの パートをチャプター・アーツセンターの前庭と中庭で行なったことは不運なめぐりあわせであった—始まりはそのように見えたかもしれない。
様々な出自の、脅えたような人々が、互いに疑いを残しながらもおずおずと近づいていって群れをなし、そしてそれが対照的な、何人かの迫害された人物たちの錯乱ぶりには関心を払わないまま親密な雰囲気で行なわれる野外のディナーパーティーの場面へ移行する、その間、私たち(時にはパフォーマーたちも)は、立ってあるいは煉瓦に座って震えていた。第三部はしかし、もうすこし暖かかった。私たちはチャプターの劇場の中に席を得て、さまざまな残虐行為の話を聞くことになった。
三場構成の『夢の体制』の寒気のする前半はしかし、おそらく偶然の所産ではなかったであろう。この夜のテーマは畢竟、ますますグローバリゼーションと民族移動で多文化主義的になってゆく世界における抑圧と紛争に関するものであったのだから。
偏見と管理の冷たい風が世界中を吹きすさぶ、居心地のいいはずがない。
これがお決まりのアジプロ演劇の夕べだったということではない。この日本のカンパニーはチャプターに三週間滞在し、アーティスト、活動家、パフォーマー、研究者などの人々と、演劇作品の創作と同じくらいに議論が重要であるようなプロセスを経てきたのである。
『夢の体制』はワーク・イン・プログレスとされているが、その滞在型ワークショップに参加していない私たちにとっても素晴らしい体験であった。
私たちはそれから、あるいは政治的、あるいは個人的、またあるいは演劇的なイメージの集積を見た。この日本の劇団は拡大し、国際的な活動家や各地域のパフォーマーを含み込んだ。私たちは力強いダンスを、自伝的な語りを、図解つきのレクチャーを—そして人々が演じるのを、しかしそればかりではなく、人々がただそこにあるのを見た。
そして一刻、私たちは手錠をしたダンサーや、ノートを取っている男や、エネルギーと力、瞑想と回避のうちに武術の動きを演じている人々からなる抽象化された演劇的場面を見、それからJacqueline Siapnoが、マイクを手につかんだ。彼女の坊やを膝にのせ、東ティモールにおけるインドネシアの残酷な迫害行為の映像を私たちに見せた—殺された身内の骨を求めて集合墓地をかきあさる人々、母子の間の自然な親密さとスクリーンに映っているものの恐怖のコントラスト。
並外れた夜であった。それらしいナラティヴや構造を持たないパフォーマンス、しかし探求、表現、挑発の媒体としての演劇性は優れて発揮され、安易な物語や解決はそこにはなかった。
参加者にとってこの経験はさらに強烈で実り多いものであったことだろう。
簡単ではない、明快でもない、そしてそれらしい「完成」もない、しかし観客としても、あたかも私たちが激しい水流の中に、数少ない石を足場に踏み込んでいくように感じたものだった。
劇団解体社は以前にもチャプターで、彼ら自身の文化を尋問に付す印象的な公演を行なっている。
今回彼らはアジアにとどまらずグローバルな問題を取り扱っている。チャプターの「Theatrum Europa 04」のシーズンのプログラムのひとつとして、私たちの緊急課題としての21世紀の新しい世界に関する議論に、彼らはより本質的で刺激的な証言を提供してくれたのである。
Review: Dream Regime
by David Adams
January 30/ 2004
The Western Mail
Cardiff, Wales, UK
It was, it would seem at first, an unfortunate coincidence that the Japanese company Gekidan Kaitaisha should present the first two parts of their performance - first on Chapter's forecourt and then in the back
garden - just as the predicted cold snap looked like it was kicking in.
We (and the performers at times) shivered as we stood or sat on walls as frightened-looking people from different nations hesitantly edged closer together, suspicious of each other until they trooped through to
what became a contrasting scene of a very cosy al fresco dinner party oblivious of the distractions of some persecuted individuals.Part three, though, was warmer: we sat in Chapter's theatre and heard about atrocities.
That chilling opening to the Dream Regime triptych, however, was maybe not such a chance.The theme of the evening was, after all, about oppression and conflict in an increasingly multi-cultural world of globalisation and migration.
Little comfort there as the icy winds of prejudice and control blow across the world.
Not that this was a conventional evening of agitprop theatre. The Japanese company have been at Chapter for three weeks, working with artists, activists, performers, academics and others in a process that has been about debate as much as theatre-making.
Dream Regime is described as a work-in-progress and was a fascinating experience for those of us not part of the residency workshops.
We had, then, a collection of images, some political, some personal, some theatrical. The Japanese troupe was enlarged to include international activists and local performers. We had powerful dance, autobiographical statements, an illustrated lecture - and people performing, but also people just being.
One moment, then, we had abstract theatrical scenes with a dancer wearing handcuffs, a man taking notes, people performing martial arts movements in energising, empowering, meditation and evasion, and then we had Jacqueline Siapno, with her baby boy grabbing her microphone, showing us film of Indonesia's cruel oppression in East Timor - the natural intimacy of the mother-child relationship a contrast to the horrors of what we saw on the screen as people scrabbled in mass graves for the bones of their murdered loved ones.
It was an extraordinary evening, a performance with no obvious narrative or structure, but a remarkable expression of theatre as a medium of exploration, expression, provocation, where there was no easy storyline or resolution.
I guess for the participants the nature of the experience was even more intense and rewarding.
It wasn't easy, it wasn't clear and it wasn't, obviously "finished," but felt as an audience as if we were stepping into a rushing stream with very few rocks to stand on.
Gekidan Kaitaisha (which means Theatre of Deconstruction) have been at Chapter before and were impressive then, when they interrogated their own culture.
Here they are concerned with not just Asia but with global concerns.
As part of Chapter's Theatrum Europa 04 season they provided more essential and exciting evidence in our urgent debates on the new world of the 21st century.
*******