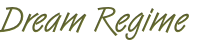戦争というややこしいもの
劇団解体社「Reflection 連鎖系」
田口寛之
身体表現によって戦争、テロリズムなどの政治的問題に立ち向かう解体社が、2004年から諸外国のパフォーマーとの共同作業として続けている「Dream Regime Project」(夢の体制プロジェクト)。その最新ヴァージョンの3部作である。すでに上演された1月の「シャーマン」、2月の「<剥製>態」という2作を繋ぐのは、両作中で映像として投影される『戦陣訓』のテキストだ。1941年に東條英機が著した『戦陣訓』は、軍人の従うべき行動規範を示していた。この中に「生きて虜囚の辱めを受けず」の言葉があったために、数多くの日本兵が自決によって命を無駄にしたのだという議論は戦後収まったことがない。戦争状況と、自殺を暗に強要する『戦陣訓』。つまり日本兵は、矛先を異にしながら暴力を義務化する点で決定的に共通していた二重の不自然な条件に拘束されていた。
それとともに2月公演で引用されたのは、アレクサンドル・コジェーヴのテキストである。彼は、世界は近代的発展の果てに、現実とは対応関係を持たない抽象化された形式だけを重んじる「日本的スノビズム」に覆われると論じた。彼がスノビズムの極みとして発見したのは、他でもない切腹だった。
ダンサーたちはぶつかり合い、痙攣し、奇声を発する。その有様はしかし、動物的ではない。内側で拮抗する複数の暴力の要請を持て余しているかのようだからだ。あるダンサーは自らを殴打しようとする。それを見る者の脳裏には、冒頭でドイツ出身のゲスト・パフォーマーが読み上げた、西独大統領による戦争謝罪の演説が再帰し、反省と自傷の概念が絡み合いはじめる。その生々しさはスノビズムとはほど遠い。
解体社の演出家、清水信臣は「劇場は戦場だ」と言う。暴力は単に近代という時代が外から要請してくるものではなく、同時に、ほとんど本能と言ってもいい欲望としてもある。自分自身への攻撃を合理化する論理は、それ自体矛盾を抱える。このややこしい戦争という事態への批判を、単純化せずそのまま提出する決然とした態度こそが、解体社の20年来の本質だ。ヒリヒリした。
ミュージック・マガジン 4月 2007