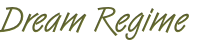詩的な身体をこえて
解体社『Reflection 連鎖系』
高橋宏幸
解体社が『Reflection 連鎖系』と銘打って『シャーマン』『「剥製」態』『「要塞」にて』という三作を1月から3月にかけてアトリエで公演した。解体社のメンバーをはじめとして、様々な国のパフォーマーたちが出演するこのシリーズに共通するのは、抽象化されてしまう、いま、あるはずの問題をあくまで具体的なものとして捉えようとすることである。それはグローバリゼーションという呼び名で括られてしまう世界において、国家や資本、権力の発生などといった様々な構造や問題が、身体という場でいかに表れているか、またはいかに現れるかということを我々の手(身体)で取り戻そうとすることだといえる。
たとえば、一作目の『シャーマン』では、ブラジルの刑務所という監獄の問題を規律=訓練化された身体としてパフォーマーたちが様々な身振りや動きをするなか、たとえそこから出たとしても管理化された社会という牢獄に閉じ込められてしまうことを見せる。二作目の『「剥製」態』では「信仰」という問題を基底に第二次世界大戦をはじめとして戦争に抑圧された身体の所在が、ヴァイツゼッカーの東西統一時の演説や大日本帝国の戦陣訓、または個人の手記が読み上げられて現れる。そして三作目の『「要塞」にて』では、天皇制が肉化された身体が問題とされる。もちろん、解体社の核ともいえる多岐に亘る思考の残滓を帯びたパフォーマーたちの身体と、その作品が抱え込む複数の問題をあえて一つのテーマなるものへとまとめてしまった場合である。
解体社の作品が見るものにとって常に極めて刺激的なのは、解消されることのない幾つもの錯綜した現在の状況を、訓練を経たパフォーマーたちの身体という容器が引き受けることによって、露呈しようとするからである。それはむろん身体の本質的な部分と個人の身体が抱える記憶を前提としている。そしてその個人から照射されることによって後ろに透けて見えてくるリアルな政治的な状況は、むしろ、身体を美化させない生々しさ、情報だけでは語り得ない剥き出しにされた身体の衝動を観客に突きつけることによってである。たとえば自動的に動くかのような右手がその本人を打ちつける行為も、パフォーマーが他のパフォーマーの背中を叩くのも時に強固な身体であるが、時に自身ですらもコントロールできない動きとなって現れてくる。
実際、これらのフィジカリティを扱った作品が孕む大きな問題は、身体中心主義として詩性を帯びたロマンティシズムへと変わることである。たとえば、アングラと呼ばれた60年代の演劇の表象などはその一端を担ったといえる。もちろん解体社もその歴史性と無縁とはいえない。そもそも詩的なものはどこにでも発生する。いわば、運動そのものの力として生というものは生まれる。
ただ、解体社が用いる政治性は、その活動の方法論と作品とが相まって、詩的なものとして回収されることを拒否する。その具体性はあくまでそこへ身体を還さない。この連作における圧迫される身体の実体性とは、いわば戦争や天皇制などの機構のもとでの、「信仰」の所産として身体がありうるということを、緊密なアトリエという極小の空間を使うことによって見ているものに刻んでいる。だからこそ、フィルターとして通過されるパフォーマーたちの身体は身体すらも批判の対象として、その反省的な方法論をさらに拡大して、それこそ外へ、グローバリズムが抱える諸矛盾としての身体や個人の位置を明確に映し出そうとする。それは、たとえ大きな物語が解体した後でも群生する諸所の問題が、一つの系となって今もって我々を覆っていることを示している。
解体社という集団は、それまでの作品との連続性を保ちながらも新たなる展開を目指している。
図書新聞2007 5/5日号