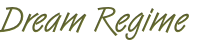グローバリゼーションの身体
内野 儀
グローバリゼーションの身体とは何か?ほとんど妄想的とも思えるこの問いを、劇団・解体社は執拗に追いつづける。グローバル化(=均質化)を体現する身体を見出そうというものでも、それに抗うローカルな身体を捏造しようというものでもない。そうした<観念>操作とは別のところで、グローバリゼーション下の<現実>に実存してしまう身体のさまざまな有り様を、美学至上/市場主義ぎりぎり手前に踏みとどまりながら、上演として記述すること。それ以上も、それ以下も目指さないこと。
一昨年行われた過去十年の劇団活動についてのレトロスペクティヴ・シリーズ後も、その真摯な芸術的/人間的態度に変化がないことは、この1~3月にかけて、久しぶりに東京で上演された新作の『Reflection 連鎖系』三部作(清水信臣 構成・演出)においても、はっきりと見てとることができた。
「シャーマン」「『剥製』態」「『要塞』にて」と題された各作品には、ブラジル、韓国、英国、ドイツ、フランスのアーティストが参加した。解体社といえば、主宰の清水と長年活動を共にしてきたメンバーの強度ある身体表現によって知られてきた。しかし、今回はそれに加えて、それぞれの参加アーティストへの「配慮」とでも言える<他者と対話する>姿勢があったために、上演全体にこれまでの解体社のパフォーマンスとは決定的に異なる感触を与えることになったのである。
各作品はタイトルにあるコンセプト/主題をめぐって展開するが、何かの明確なメッセージを伝えようというのではない。世界各地から集結したアーティストに解体社の俳優が加わり、一方で、たとえば、ブラジルにおける監獄の悲惨な状況や第二次世界大戦の記憶についての俳優の個人史とかかわると思しき語りが静かに敢行される。他方で、同時代の社会政治的位相に置かれたさまざまな人間の関係や身振りが息苦しくも鮮やかに切り取られてくる。素朴な太鼓の伴奏とともに空間にうごめき衝突する身体から、ただなすすべもなくゆっくりと空間を横切っていくゆく身体。あるいは、何かに憑かれたように自虐的に振る舞う身体や痙攣がとまらずに叫び出す身体まで。さらにスクリーンには、主題とかかわるアレクサンドル・コジェーブの「動物」をめぐる一節や戦後40年当時のドイツ大統領リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーの演説の言葉などが映し出されもする。
戦争の記憶という歴史性と「動物化」して暴力に支配される現代世界という同時代性。それらが主題化されていることは明らかだが、上演はそうした主題を押しつけるわけでも、それらの主題を遠くにあるものとして可視化するわけでもない。構成・演出の清水は、参加したパフォーマーたちとの<対話>を通じて、怒ることも嘆くこともなく、世界の<現実>を、ただそのようなものとして、そのようでしかないものとして、空間にそっと置いてゆく(だけな)のだ。
この連作が衝撃的なのは、おそらくこの置き方の手つきとでも呼べるものがあるからである。解体社の上演は観客の凝視も、あるいはその思考すら要求しない。そこに置かれた身体たち同様、観客もまた、上演を自身の眼にただ単に投影する身体でしかないことの<謙虚な認知>が求められるのである。そう、ここで繰り返し告げられるように。「与えるな 捧げるな 眼差すな 映させよ 世界を この眼球の表面に」。
芸術新潮2007/5月号