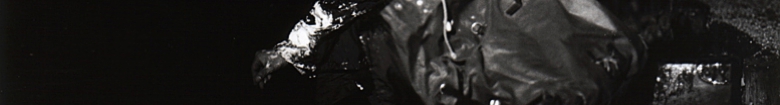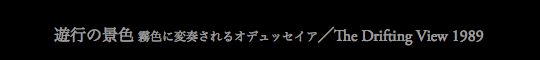演劇という制度への反省を促す
『遊行の景色』解体社 利賀フェスティバル公演
鴻 英良
演劇を表すシアターという言葉はギリシャ語のテアトローン、つまり、観客席を原義とするというようなことは、かつて演劇雑誌では頻繁に言及されていた。これは観客がいなければ演劇ではないということであり、しかも、観客席はイメージとしては固定されたものだということである。野外劇場というものは劇場の形態としては、日本でそれほど多くないが、この特殊に見える劇場でも、観客席はあり、それはだいたい固定されている。
ところが観客席を固定させるのはよそうではないかという、かなり、大胆な試みをつづけている劇団がある。この試みは思いのほか困難な試みであり、必ずしもうまくいくとは限らない。この劇団解体社の演劇はいまだ試行錯誤を続けており、そのこと自体もこの劇団の試みを魅力的なものにしている。
この夏、解体社は二つの公演を行った。一つは利賀フェスティバルでの「遊行の景色」、もうひとつはヒノエマタ・フェスティバル89での「遊行の景色5」。ふたつとも基本的にはホメーロスの「オデゥッセイア」の流浪のイメージをもとに劇を構成し、文字通り、役者は演じながら場所を転々としていき、観客はその役者たちを追いかけるという構成をとっていた。ただ利賀村の場合、あまりに観客の数が多く、彼らがなにをやっているのかあまりよく見えず、しかも豪雨にたたられ、台詞もよく聞こえないということもあったし、その他、いくつかの問題点もあったのだが、雨に邪魔されながら、広場から河岸道路、さらには河原に組まれた巨大な舞台へと場所を変えながら、役者は演技をかさね、そして最後に橋を渡り、河むこうの道路を去って行くというこの〈移動演劇〉は時折、美しいイメージや、空間の奇妙な歪みを見せていて面白かった。台詞といえば「オデゥッセイア」という言葉が聞こえる以外、何も聞こえなかったと言っても過言ではないようなのに、演ずる場所を常に変えようとする演劇は旅芸人の姿を劇場に閉じ込めることなく、われわれ観客に提示しようという試みであり、近代的な〈幽閉演劇〉にたいする異議申し立てであり、観客席の〈牢獄化〉にたいする断罪なのだ。
こうした主張がそれなりの正当性を持っているということは、彼らの移動を目で追いながら、われわれ観客はかなり自由に振る舞うことが出来るし、どこから見るかは予想以上に観客の意志に委ねられていることからも明らかである。近くからは見えにくいときは遠くに引き下がり、椅子の上に立ってみる。そうした観客たちが作る構図がまた美しく、観客自体が役者が組織する構図とは別なイメージを作り出し、私は時折、そうした偶然のイメージの美しさにみとれたものだ。
こうして観客の中に迷い込むようにして、「遊行の景色」をみていた私は遊行する旅芸人が生み出す景色の中には演劇の本質である観客のイメージの再生すら含まれていたのだということに思いいたったのである。劇場の観客席でうしろを振り向くときのバツの悪さというのは、見るものの視線の自由を演劇が奪っていることの結果に他ならないのではないのか、われわれはいま演劇という制度にたいして根本的な反省を試みなければならないのではないか、解体社の公演を見ながらそう思った。
モノ・マガジン 10/16号 1989年