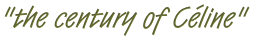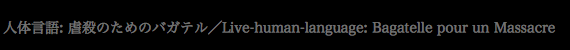アートの公共学
解体社ーセリーヌと「動物」をめぐって
高橋宏幸
いまセリーヌを、その文脈について
ここ数年、解体社がフランスのコラボラトゥール(対独協力者)であり、反ユダヤ主義者として糾弾を受けた作家、ルイ=フェルディナン・セリーヌのテクストを使って、もしくはセリーヌを通して作品を作ることを試みている。二年前にはセリーヌの作品をモチーフとした三部作が作られた。その時は率直のところ、いまセリーヌを取り上げることがどの文脈によるものか、いささか唐突に映った。再びセリーヌが話題になっているとは、とても思えなかったからだ。一般的には『夜の果ての旅』の作家として知られているだろうが、それ以外の著作が広範に読まれているとは思われない。欧米では反ユダヤ主義者であった余波で読むことができないテクストもある。たとえ日本では全集が出版されているとしても、特別いま注目されているとはとても言えないだろう。
しかしセリーヌの作家性とは別に、反ユダヤ主義者でありコラボラトゥールの作家としての文脈は、かつてならば福田和也の『奇妙な廃墟』に描かれたように、消された作家たちの系譜に連なる。反近代を謳ったものたちが民族主義やナショナリズムと結びつき、ある点を超えると背反するはずのアナーキズムや左派のイデオロギーと親近性を持つ。そのような現象は、なにも当時のコラボラトゥールたちだけに限らない。たとえば、アンダーグラウンド演劇を含めた、ニューレフトたちの浪漫的な要素との相関関係も透かして見ることができる。
90年代の小林よしのりの『ゴーマニズム宣言』や加藤典洋の『敗戦後論』など、右傾化や左翼の後退と思われた頃から時代は変わっても、いや、その状況はより進み、グローバリゼーションの動きは、保守や右派の隆盛と同じく、左派を含めて双方から反グローバリズム運動を生み出している。それは、ポリティカル・コレクトネスの息苦しさも相まってトランプを誕生させ、ブレグジットやイスラミック・ステートですら、その中に位置づけることができる。かたや左派の反グローバリズム運動は、グローバリゼーションという新しい資本主義、もしくは国歌を超える資本の欲動への批判として、ローカリティを擁護する。左派が弱体化しているとしても、反グローバリズムの動きは顕著にある。むろん、卑近な例ではオリンピックをはじめ日本を鼓舞する動きは、落ち目の国家にありがちなナショナルのものを喚起する快楽だ。それらはテレビ番組をはじめ、ポピュラー・カルチャーなどありとあらゆるところで散見される。ウェブやSNS界隈でたむろするネトウヨやパヨクたちの一喜一憂する応酬はその顕著な例だ。
そのような状況の表象として、または深く批評するために、セリーヌという作家が取り上げられたのだろうか。ただし二年前の『セリーヌの世紀』と題された三部作は、三作目は未見だが、試行錯誤の段階という感があった。三部作それぞれにセリーヌを代表する作品のタイトルが冠されていたが、大まかな印象ではまずセリーヌそれ自体を説明することがあった。そして、いかにテクストを扱って、作品へと結実するべきか。いままでもテクストは使われていたが、いつにもまして解体社がテクストを扱い始めたことに挑戦していた。いわば身体や空間を構築するためにテクストはあったが、テクストが身体を読み込もうとしたのだ。しかもより鮮明に一人の作家のテクストをモチーフにした。それは、単なる新しいシリーズというだけではない試みとなった。
身体 (人体) とセリーヌが交差するところ
最新作である『人体言語/虐殺のためのバガテル』は、それらの段階を経て、いくつもの文脈が混じり合う、重層的な作品へと進化している。解体社のアトリエでもある市ヶ谷の左内坂スタジオで、その公演は行われた。いまどきアトリエをもつ集団は珍しいが、それがあるからこそ、今もって特異な表現活動を継続できる強固な集団性が備わっている。
その文脈の一つにあるのは、いままでの解体社の作品にも現れている身体性の問題だ。あらゆるものに抑圧される身体の位相を提示しながら、そこに抵抗としての身体の強度を映す。いわば、生政治のなかへと取り込まれた身体、解体社の言葉でいえば、パフォーマーたちの「人体」を、剥きだしの生として暴き出すことがある。このアガンベンの唱えたモチーフは、一時期、解体社のパフォーマーの身体、もしくは作品そのものの指標となった。その後の2010年代の初期に行われた一連の作品たち、ポーランドの劇団、テアトル・シネマとの共同制作のテーマである「ポストヒューマン・シアター」も、そこに関連する。
そのテーマによって作られた作品群のなかから、シーンを一つ挙げてみる。パフォーマーたちが一心不乱に同じ身振りでひたすら踊り続けることがある。背景の映像では、崩壊したリビアのカダフィ体制と、その希望的理念が流される。それを前にしたダンスは、アメリカというグローバリズムの「帝国」が、デモクラシーの限界とも言えるだろうが、そこからはみ出たものたちに与える帰結を示すようだった。あえて名付けるならば、「カダフィ・ダンス」は、暴発的な身体とひたすら同じ身振りを激しく繰り返す、もしくは繰り返すしかないように仕向けられる状態となる。まるで、その先には死しかないということが端的に表される。むろん、カダフィ体制が良いとか悪いとかいうレベルの話ではない。さまざまな場所で行われるアメリカ的正義の介入は、正義が正しいシステムとされてしまった以上、システムによってそこに生きることしかできず、その正しさを生きるしかないのだ。
それはそのような世界の人間でいることを構造として強要されている。だから、人間というものの後に、人間はいかにあらわれているのか。それはポストヒューマンやサイボーグといってもいいし、動物といってもいい。その言葉が出てくる背景には、少なくとも、従来の言葉で人間なるものの位相が捉えられなくなっている現状がある。
もう一つの文脈は、そこで使われるテクストたちにある。それらは、とくにセリーヌなどのテクストを通して読みこまれる身体だ。セリーヌのテクストをパフォーマーが発することはもちろんあるが、単に物語りを追うことはない。それらのテクストの断片の言葉たちによって身体もまた一つの読まれるテクストとなる。
そもそもセリーヌの作品たちは、いわゆる物語の筋を追うものではないだろう。そのエクリチュールである、呪詛にまみれたかのように書かれた言葉たち、文体にある。フランス語のできない私にとって、しばしば語られる文法の規範を無視して、うねるように書かれたとされる文章は、日本語で読んでいるだけではとくに掴みづらい。しかし、恐れずに言えば、そのようなテクストを解体社は身体で読み、提示しているといえるのではないか。いわば、強度と錯乱というエクリチュールが身体の場に変換される。いくつもの文脈や層が重なると述べたが、それはエクリチュールのみではない。先に述べたいま上演することの必要性ともいえる外在的な状況も含まれる。セリーヌの反ユダヤ主義の呪われた作家としての面だ。芸術と倫理とは切断できない。その両方を抱合してしまう美がある。しかし、だからといって、単に許容はできないだろう。それは差別するもの、されるもの双方の立場において残る。それはポリティカル・コレクトネスそのものであると同時に、そこに覆われた世界においては、それを突破するための文脈として読まれてしまう危険性もある。
今作で扱われるテクストは、確かにセリーヌを主調としているがそれだけではない。水平社宣言から始まり、セリーヌの反ユダヤ主義のテクストの出版を許諾しない未亡人の書いたテクスト『セリーヌ 私の愛した男 踊り子リュセットの告白』もある。それは夫への愛を綴っているが、同時に夫が書いたテクスト『虐殺のためのバガテル』の引用と両立している。タイトルにもある『虐殺のためのバガテル』は、日本語訳では『虫けらどもをひねりつぶせ』として出版された。セリーヌの反ユダヤ主義の論調がこれでもかと含まれている。また、その反響はどのようなものだったのか。当時のフランスの書評も多分に引用される。
他には、デリダの晩年の思想であり、講義や講義録として残されたまま未完に終わった「動物論」などもある。扱われたテクストだけを述べると、それは多岐にわたると同時に、恣意的なものに映るかもしれない。しかし、これらのテクストに理由があることは確かだ。たとえば、デリダはユダヤ人であり青年期まで過ごしたアルジェリアで差別を実際に色濃く受けている。
一見すると、解体社のパフォーマーたちの身体と作品の形式自体に劇的な変化があったわけではないかもしれない。しかし、解体社の蓄積とその深度によって、まるで同じところを巡っているようでありながらも、それこそ二つの楕円のごとく、それは徐々に重なりながら、いつのまにか新たなる試みのものへと生成変化を遂げようとしている。
『人体言語/虐殺のためのバガテル』
『人体言語/虐殺のためのバガテル』の舞台の表象は、一見したところ、いつもの解体社の基調に沿っている。たとえ、かつてに比べたらテクストを扱う量が増えたとはいえ、身体性の演劇であり、パフォーマンスという基軸は変わっていないからだ。パフォーマーたちはそれぞれに自己の身体と関わる様々な行為を行っていく。ただし、それがテクストの持つ負荷とともにある。まるで、読まれていくテクストと身体が共振するかのように、身体がテクストに読まれると同時に、引用されるテクストもまた身体性に包まれる。
冒頭、薄暗い中から現れる一人の男によって、「水平社宣言」が、とつとつと読まれる。「人間に光りあれ」という高らかな宣言とは裏腹に、そのパフォーマーの身体は、まるで見えない何かを恐れているように小刻みに震え続けている。その宣言の持つ意義は、作品が進むにつれて分かる。それこそ「動物」という問題と接続されるからだ。
被差別者であれ、人間性の中に人間の誇りを見出す宣言は、人間を中心とした視点に立っている。ではそもそも獣と人間を分かつものとはなにか。むしろ獣という視点から人間を見つめることによって、人間なるものを脱構築するのが、デリダにおける動物の概念だ。それはデリダの思想を借りるだけでなく、この作品を通して提示されていく身体性だ。いわば、舞台を通して人間もまた動物であり、動物の身体であることが描かれる。むろん、最初のシーンだけではそこまではわからないが、この「水平社宣言」もいつもの解体社の引用するテクストの一つという意味を持つだけではない。別の文脈も伴っている。
そのシーンのあとは、セリーヌの『虐殺のためのバガテル』はもちろん、その他のセリーヌのテクストや、セリーヌの妻の残した告白、いくつかの寓話なども散りばめられて、パフォーマーたちの身体の状態が細部にわたって露わになる。静謐な緊張感のある空間は終わりまで一定の重さのように維持される。いつものように仄暗い舞台のなかで鳴り響く重低音のあるサウンド。民家を改造したアトリエ空間は大きな窓からの街の光や微かに入る音など、劇場とは違って自在に外部の状況を受け入れる。
たとえば、セリーヌの妻のテクストを語るシーン。まるで実際の小部屋に置かれた小さなテーブルと椅子に背中越しに座る一人の老いた女性は、壁に掛かった絵に向かって、かつてあった失われた時を求めて、セリーヌとの愛おしい記憶を紡ぐように話す。舞台の片隅のはずが、そこは実際の小空間の空間も合間って窓辺に思えてくる。それはセリーヌの妻の役を演じるとはいかないまでも、非常に演劇的なシーンといっていい。しかし、そこから単純なシアトリカリティにおもねらないのも解体社ならではだ。テクストが使われて、そこで読まれる妻のセリーヌへの愛情の物語に観客を引きつけることもできるはずなのに、同時に拒否されるのだ。
舞台が進むにつれ、徐々にセリーヌの反ユダヤ主義のテクストがいくつも言葉にされる。パフォーマーたちの身体もあいまって、ある熱狂を帯びたものへと変わっていく。それぞれの身体性をモチーフにした動きにも関係してくるからだ。いつものパフォーマーたちの動きも、まるで斜めから見る視点が挿入されるように違って見えてくる。地面に敷かれた鏡の上で照り返される身体や、四肢がまるで切り裂くように動いたり、何かにうなされるように震えたり、動物の身体と接続されるように自身ですらコントロールできない人体。一つ一つを取り上げれば、それは過去の作品にもあった動きであるかもしれない。しかし、わずかであれ異なる文脈にも置かれると身体も変容をきたす。
たとえば、鏡のようなものの上で示される身体は、それこそ見られる身体だ。見られている身体を照り返すように相手に見せるということも解体社のふだんの方法だが、そこでの身体もかすかな差異がある。観客を照らし返すことはことはもちろんだが、鏡からも映される身体は見られることの恥ずかしさがある。デリダが語るように動物に裸を見られて感じた恥ずかしさという人間としての身体をいかに提示するか。それは観客とパフォーマーが同時に動物として対置される瞬間だ。その間である、見ることと見られることによって、動物としての人間の身体が生まれる。
また、あるシーンでは背景の字幕に当時セリーヌの反ユダヤ主義の本がいかにスキャンダラスに賛否両論を巻き起こしたのか、その書評が流れる。いくつもの身体のパフォーマンスが作り出した空間は、ときにマイクを使ったナイチンゲールズの寸劇のようなシーンも入れ込まれる。それは、空騒ぎのような奇妙さといえる。その空虚さはおそらく差別とファッショという二つのものが混ざり合った、戦間期から二次大戦期へと移行するフランスの独特な空間をも想起させる。どれだけ熱狂が渦巻いても、それは笑いというおかしさの中にあったのではないか。その飽和点は熱狂の果てにある、からっぽなものであり、セリーヌのテクストの熱っぽさも無化される。
だからというわけではないだろうが、終わり近くには全員のパフォーマーたちが舞台に立ち並び、再び一心不乱に震えつづける圧巻のシーンがある。それはまるで最初のシーンに戻ったように、ひどく緊張を強いられて、逃れようのない身体たちだ。熱狂のなかで享楽に浸る身体とは違う。享楽に浸りたくても浸れない、必ず裂け目のように亀裂が入れられる。それはいわゆる両極にあるもの、もしくは複数性ともいえる、いままでの解体社の読み方とも違う差延がある。あることを提示しながら、しかしそれもまた同時に批判される。セリーヌのテクストを用いつつ、セリーヌが批判(吟味)されるといっていい。
新たなる試みとしての動物
実際、セリーヌ意外に引用されるテクストには、講演や講義録のままで終わったデリダの晩年の思想、『動物を追う、ゆえに私は(動物)である』の一説から動物に関する引用もある。先に述べた獣である動物とそれは深く関わり、そこにもまた差別と反差別という両極がある。自身もまたアルジェリア出身でユダヤ人として差別を受けていたデリダは、当たり前だがセリーヌの反ユダヤ主義のテクストとは真逆のものだ。むしろ、そのような人間的な、あまりに人間的なものを徹底的に脱構築するために動物の視野がある。また、前号で述べたがこれまでの解体社の文脈でしばしば取り上げられていた、身体のテーマと関連する剥き出しの生を唱えたアガンベンも、デリダの講義録『獣と主権者』では批判される。それも人間という枠を超えていないということからだ。
もちろん、デリダはアガンベンとの差異を見つけようと批判したのだろうし、解体社はセリーヌと剥き出しの生、ときにそれは近似的なものに映ることに対して、動物という両極なはずのものを置くことによって新しい思考と身体の場を開こうとする。いままでの解体社の文脈である剥き出しの生とセリーヌのテクストを蝶番させるものとして動物がある。舞台に置かれるパフォーマーたちの身体を通して示される位相は、主権者として人間そのものの固有性と思われていた政治を脱構築する契機を、身体のなかに全き他者である動物として見出そうとする。
だから、冒頭のシーンは幾重にも意味を持つ。リテラルには「水平社宣言」としての差別という問題。それは被差別以外にも、むろんユダヤ人問題なども含まれる。しかし「水平社宣言」自体もまた、時代の限界であり段階的に必要なものだったとしても、人間であるということでは人間を中心としている。では、動物というものを対置すればどのように映るのか。それは、剥き出しの生としての身体=人体もまた再び問い直されることだ。
だから、自らの今までの作品を煩悶するように、反復を繰り返しながら、差異が見出されていく。それは同じような基調を伴っていても、違う文脈が、ときにそれはラディカルに、ときにわずかなズレとして舞台には現れる。その意味において、解体社はかつての「ポストヒューマン・シアター」を継承しつつも、セリーヌを通して新しいことを開拓しようと試みている。しかも、それは大げさにいえば、デリダが未完のままに終わった動物という問題を、スノッブとしてポストモダンの果てに現れたコジェーヴが唱えた動物とは違う動物というものを身体に落とし込もうとする。
かつての三部作ではセリーヌのテクストを通して、単にナショナリスティックな現代を穿とうとしたのではないかと思われたことは、はるかに後景に退いた。むしろセリーヌのテクストであるからこそ、抑圧や熱狂といった幅広さのなかで動物としての身体が提示される。その意味では解体社の射程は、はるかに深く広い。まるで、来るべき世界への問いかけを身体という場で行おうとしているようだ。
(演劇批評家)
テアトロ 2018年/7ー8号 アートの公共学 8ー9