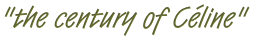劇団解体社「セリーヌの世紀」三部作
第三部 夜の果ての夜
強烈な身体表現で作者に向かう
今野裕一
舞台が始まると、作家セリーヌがどんな人であったかの解説がスクリーンに流される。そしてパリのパッサージュ(アーケード)の映像が投射され、セリーヌの生きていた時代に観客は次第に呼び込まれていく。スクリーンの背後から、看護婦のように見える人やチョークで字のようなものを書き続ける人、踊る人、痙攣する人、自分を叩く人、いろいろな人が出てくる。どこか普通ではない。セリーヌの言葉を使って精神療法をしている精神病院のようにも見える。
そう見えるがそうかどうか確かめる方法はない。解体社の演劇は伝えるように分からせるように演出されていないからだ。そこにセリーヌの思想や時代背景が「ある」ように描かれている。観客は積極的に頭を働かせながら見るようにできている。「夜の果ての夜」は、小説を脚本仕立てにしているわけではなく、小説や作家自体を構成・演出の清水信臣独特の方法で役者の身体に落とし込んでいる。
1985年の結成以来、解体社は、時代ごとにテーマを追求してきた。時には、天皇制、憲法第九条のような政治的なテーマにも取り組んでいる。一貫しているのは、テーマを身体に刻み、それを極限の状態で表出させるということだ。いつまでも痙攣し続ける身体、相互に叩きあう身体・・・それはこれまでにも強烈な衝撃を観客に与えてきた。その身体に言葉を向かわせるのが解体社だ。
解体社を長く支えてきた熊本賢治郎、日野昼子、中嶋みゆきをはじめとする役者群は、今回も強烈な身体表現でセリーヌに向かっていったが、セリーヌの言葉と身体が交錯するある種の混沌を見ていると、セリーヌの反ユダヤ主義を単純に否定すること自体が、その時代の闇をもたらしたのではないかとすら思えてきた。
公明新聞 4月8日 2016年