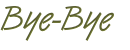声高に語るアクション
Carol Martin
男は挑発の色も見せずに、繰り返し、激しく、身じろぎもしない女の背を打つ。灰色にペイントされた彼女は、奇妙な冠をかぶっている。殴打の度に彼女から、日本の天皇の名前や、アッシリア、ハンガリー、クリミア、朝鮮などの地域の名前が吐き出される。時々ランダムに提示される英語のセンテンスだけが彼のテキストだ。観客の忍耐力を大幅に超えながら、この場面はその始まり同様に非儀式的に終わる。男は、女が立ち去った後、今度は激しくリズミカルに、倒れるまで自らの両腿を打ち始める。パフォーマーは奇妙なまでに受動的であり、まるで彼/彼女ら自身より強大な何かの力を拝受するかのようだ。
これは10月4日、ジャパン・ソサエティで開催される日本演劇シーズンの幕開けを飾る清水信巨演出、劇団解体社(Theatre of Deconstruction)の「バイバイ/未開へ」のワンシーンだ。今シーズンは解体社に加えて、アジア・パフォーマンス・フェスティバルや実験演劇の演出家として著名な鈴木忠志の作品が紹介される。
「身体はフィクションではありません」清水は東京にある彼の稽古場にて行ったインタビューでこう答えた。「身体は文化的構築物であり、現実のドキュメンタリーの一形態なのです。」清水の演劇において、パフォーマーは「shintai」、つまり身体表現を —これは舞踏として知られる日本のダンスの本質でもあるのだが— エモーショナルな意味よりむしろ身体的な意味を生み出す為に用いている。清水にとっては、運動とジェスチャーから創られる演劇こそ、身体が生み出す様々な意味を情報テクノロジーに支配された世界から救う唯一の術なのである。「今日、身体は難民である」と彼は断言する。
清水の演劇は、日本の世界経済支配は一時的なものだったことが明らかになった1990年代に出現した。グローバリゼーションは、ある人にとっては、ユートピアへの二度目のチャンスに映っているようだ。新たなアイデア、政治的視点、諸々の経験やアートは、グローバル・ワールドにおける自由主義ムーブメントの製品として機能していた。しかし、これらは実際には起こってはいないのです、と清水は言う。その代わり、急速に相互に繋がれたネットワークによって縮小されていく世界は、同質性を再生産しているのみであると——つまりアメリカ化された世界文化という、どこにおいても同じ様な免税店が並んでいるような終わりなき連鎖。閉所恐怖的な現象が今起きているのだと清水は言う。そんな状況の一つである「ヒキコモリ」と呼ばれる現象では、何万もの日本の若者が社会から引き篭もり、働くことも通学も、そして家から出る事すらも拒絶している。
勝利の後の敗北感は、19世紀中頃から日本において繰り返し論じられてきたテーマである。日本の演劇批評家である内野儀は、1995年に起きた阪神大震災とオウム心理教の東京地下鉄ガス襲撃事件が、日本人に原爆による敗北の記憶を呼び起こしたと指摘する。代わりに目立ち始めた外国人の存在は、一部の日本人を外国人排斥運動へと導いている。これらの狂信的愛国主義や人種的不寛容さはまさに劇団解体社がその極端なまでのフィジカルな演劇で問い直すものなのだ。
支配と非支配、強制、制限、サディズム、マゾヒズム、ファシズムは、清水の演劇において、身体の行為として繰り返し探求されている。マスクを被り上半身裸の女性が胸を押さえながら始終飛び跳ねる、パフォーマーたちがお互いに見た限り全力でクラッシュする、生きる望みを失ったさまよえる人々がそれでもユートピアを探し求める、そんな場面を彼は繰り返し提示するのだ。清水の演劇では、英語のみが使われる — 日本人にとって認識できるが解読不可能な言葉。コミュニュケートを図ろうとする試みは、絶えず暴力として帰結する。この世界において、言葉でなにか意味のあることを表現することは不可能なのだ。「英語と暴力、この二つこそ世界が共有しているものなのです」と清水は苦々しく語った。
清水は複雑な思考を語ろうとする演劇を生み出すことがいかに難解であるか、非常に意識的である。「唯一の現実、真実を伝える可能性を秘めた残されたドキュメントは、身体です。演劇における身体こそ、複雑で矛盾に満ちた21世紀の生の経験を伝えうる唯一の媒体なのです。」身体が語る真実が一体何であるかを語ることは、容易ではない。体は嘘をつかないという考え方は、心理的な真実ではないだろう。それは入念に練られた劇的な台本の語る真実でもない。清水の演劇にある本能的なシナリオは、支配的な世界関係の直中で悪化している個人主義、地方のアイデンティティ、国家アイデンティティを描き出しているのだ。
「カンバス」(劇団の稽古場)のある湯島は、古くから東京の下町だった。有名な湯島天神も、東京大学のメイン・キャンパスと同様、近所にある。何千人もの学生が試験の成功を祈願するために神社を訪れ、小さな木の板に願い事を残していく。湯島は流行発信地でも文化地区でもない。そこは現代生活が伝統といったもので活気づき、学生と居住者が、古くから続いている小売店や下宿、安食堂、そして言うまでもなく神社といった場で共存している場だ。清水の演劇的感性は、解体社が今や世界ツアーのマーケットに乗り出していることから分かるように、この地区の印象を越えたインパクトを持っている。彼の作業は舞踏の始祖である土方巽のみならず、ピナ・バウシェやロバート・ウィルソン、タデウシュ・カントールの影響を受けているように見える。ヨーロッパでは、ベルギーの演出家・ヤン・ファーブルともしばし比較される。劇団解体社は、ジャパン・ソサイエティの他に、ドイツと英国の諸都市でもツアーを行う。2002年にはメルボルンで開催されるネクスト・ウェイブ・フェスティバルにも参加する予定である。
1985年に創設された劇団解体社は、オルタナティブスペース、映画、視覚芸術、インスタレーション、音楽、そしてダンスの持つインパクトを演劇において実験してきた。清水は作業を、人種差別、ジェンダー関する偏見、性役割に潜む矛盾、政治的虚偽に対するラディカルな批判として捧げている。清水の目的は、まさに芸術を通してこの世界を変革することなのである。彼は劇場を個人と集合体、隔離と威圧の間の緊張関係を探索する理想的な手段として考えている。
解体社の悪名高き殴打の場面は、1996年のザグレブ公演では騒動を引き起こす直前にまで至った。観客はまず口笛を吹きはじめ、次第にその暴力をやめさせようと「Stop It!」と叫んだ。アジテーションはエスカレートし、ついには最前列に座っていた男性が立ち上がり、犯罪者たるパフォーマーに掴みかかり、ひっくり返した。しかしこの阻止行動を歓迎する観客の反応にもかかわらず、パフォーマーは立ち上がり、再び女の背を叩き始めたのである。内戦直後のザグレブにおける観客はこれにより、ある美的な舞台を妨害したところで、象徴的な意味においても、世の中の暴力を止めることにはならないのだと理解したのだ。
より地域性に直結した見方をすれば、清水が暴力の問題を日本の天皇の名前と関連づけたことは、論議を呼んだ小泉純一郎首相の靖国参拝の問題を想起させる。日本の戦没者を奉る神道の碑物は、天皇崇拝や軍国主義と密接に繋がっている。日本人を含めた多くのアジア人にとって、靖国参拝は第二次世界大戦の惨禍を認識拒絶していることを意味する。中国南京侵犯や、韓国人を筆頭に多くの女性が日本兵のために性奴隷として無理矢理働かされたことは、その他の様々な事件と同様に未だ生々しい。20人の若い韓国女性たちは、小泉首相の参拝に抗議するために、自傷暴力の形で小指を切り落とした。
ザグレブにおいて芝居は勝利した。それ以後は中断する事なく、パフォーマンスがやり遂げられたのである。しかし目の前の舞台で繰り広げられる残虐な攻撃に対する諦めは、日常生活において増加している暴力への無力さにどこか似ていると、パフォーマーも観客も実感させられたに違いない。清水は言う「生身の身体に宿る暴力の攻撃性を、私はこの作品で自殺させたのです。」
The New York Times (23/Sept. 2001)