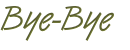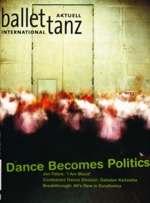どのように日本人が我々にグローバリゼーションを突きつけるのか
現在、日本で最も重要なダンスグループがヨーロッパツアーを敢行。クラウス・ヴィッツェリングがフランクフルト・デュッセルドルフ公演に先立ち、ハンブルグ「ラオコオン・フェスティバル」のオープニングを飾った、センセーショナルなツアースタートを観た。
Klaus Witzeling
半裸の若い女性が、根が生えたようにそこに立っている。右手が時折ぴくっと動く。腿の内側の筋肉が震え続けている。何分もの間。ベトナムの少女がショックで泣きながらカメラにむかって走ってくる写真が脳裏に浮かぶまでには更に時間がかかる。記憶の中に燃える、一枚の忘れがたい写真。しかしすぐに忘れてしまいたい写真。日本のカンパニー劇団解体社が、ラオコオン・サマーフェスティバルのヨーロッパ初演「バイバイ/未開へ」で、それを容赦なく記憶に呼び戻し、観客を回想の中で改めて戦争犯罪の無力な目撃者にする。
この身体パフォーマンスの観客は、途方に暮れた無力感にそれ以外にも何度か襲われる。薄暗い中で男性の集団が一人の女性を追い立てる。彼らの身体は暴行的抱擁で思い切り衝突する。やがて戦闘ヘルメットをかぶった別の女性が登場する。長い尾をつけ、ねずみ色に塗られ、パンツしか身につけていない身体が、ナイフを機械的な反復で、攻撃するように振っているにも関わらず、生気なく見える。単なる非情な戦争マシーン。彼女の背中は、パートナーのちょうど20回の平手打ちに耐え、その度に口からは叫びの代わりに紛争や内戦、 ジェノサイドに悩まされたヨーロッパや第三世界の国名が吐き出される。
舞台上で沈着かつ無情に遂行される暴力行為は、皮膚の下で不快に這い回る。夕方のニュースの恐ろしい映像の時のようにチャンネルを変えることはできない。一人の若い男性が、皮膚が破れんばかりに掌で太腿を絶え間なく叩き続ける。感覚を無くした身体や麻痺した感覚器に再び感覚や命を吹き込もうとするかのように。
トラウマを受け麻痺したこれらの人間。生きる屍。彼らの四肢は切断され、身体は傷つけられ、包帯に巻かれ、義足をつけている。「バイバイ/未開へ」は、苦しいほどにゆっくりかつ静かな動きのイメージで、身体を戦場として提示している。そして演劇を戦争として。「これらは身体を利用し、かつ消費可能にするのです。」と演出家の清水信臣は言い、「解体の演劇」(文字通りの解体社の訳)の中で、その作用を証明している:戦争に駆り出される身体、戦争を生き延びた身体を見ることができる。聴覚・視覚的に、映像シークエンスで戦争地獄が表現されている。
そして嵐の後再び、致命的静寂が支配する。無言で指令がスクリーンに流れる。戦争が終結する中、全てが新たな未開へ、そしてメディア網に連結され、グローバルに操作された湾岸戦争における感情の荒廃へと向かう序章である。
彼はもともと、役者とダンサーになりたかった。しかしその後彼の計画は変わり、演出家へと向かった。1985年、清水信臣は劇場の外に出た。型にはまった演技やおどりを無効化し、移動型(野外)演劇をヒノエマタ・パフォーマンスフェスティバルで始めた。"The Drifting View"の上演の一連では、観客は役者と共に野原や河原、公園を歩き続けなければならず、身体を媒体オブジェとする"Theater of Images"を体験した。湾岸戦争やルワンダの民族虐殺におけるメディア体験やエイズ、グローバル化、インターネット革命による社会的、政治的変化が、清水を更なる芸術的転機へと導いた。
しかし清水にニヒリスティックなペシミストの烙印を押すのは、彼を誤解することになる。彼は、過去に隠蔽された問題や、明白な暴力行為としての政治・メディアが、公の意識の中に残した痕跡に固執している。「均質に見える日本社会というのは完全に幻想です」と彼は言い、公には無視あるいは沈黙させられている多文化地区や移民ゲットーで、貧困や社会的緊張が支配する、東京内の南北問題を挙げている。現代の「日本演劇界のロマン主義的リアリズム」は、民主主義や平和主義の仮面に隠れた、温和で反動的、排他的な演劇であるらしい。彼はそれに対しラディカルな身体演劇で挑発する。その表層を解体し、皮膚の限界である甲羅の下に入りこもうとし、個人史、社会史の記号的身体カリグラフィーの記録を剥き出しにする。
彼は、彼の身体演劇の中で皮膚をテーマとしている。パフォーマーが叩いたり、身体の内側と外側の皮膚の線を柔らかくするようなことを、「私はメソッドとは呼びたくありません。なぜならグループのメンバーは皆、それぞれの神経系を持っているからです。それぞれダンサーなり役者なりの異なる訓練や身体コンディション(体質?)を持っています。それを活性化するために、一人一人に合った方法を見つけるよう努力しています。」彼は現在「幻影体」に取り組んでいる。「それはファンタジーです。切断された足の動きや四肢を失った生きた身体の感覚が我々の知覚システムに再び明らかになる。神経が身体システムの中でどのように作用するのかを正確に知りたくて、研究しています。」
稽古の過程は見かけ上は混沌としていると清水は言う。「私は様々なインフォメーションを実験しています。一つの音やテーマなど、一つ要素を与え、杭を一本一本列になるまで打つ、その発見の過程を動きに促していくのです。一つのフォルムから、いわば次のフォルムを見つけることができるのです。」
芸術的展開の中で、一般には誤って理解されていると彼が言う、土方巽、そして解体社のスタイルに転化したマーサ・グレアムのコントラクトの技術やピナ・バウシュのダンスが彼に影響を与えた。「彼女は私に、ジェンダー問題、男女関係の問題性を意識させましたが、彼女から影響されているとはいえません。我々は、我々以前の芸術家を知り、彼らがモダン以後、身体をどう理解し使用してきたのかを知らなければなりません。歴史の知識は私にとっては不可欠なのです。」
日本演劇の身体認識は、先世紀の後半、幾度となく変化してきた。1960年代、身体存在が舞台上でテーマ化されたが、20年後には身体存在の可視的シグナルは再びタブー化した。「身体はそこに存在しているにもかかわらず、舞台上で消えたかったのである。」と演劇批評家で将来のラオコーンフェスティバルディレクターである鴻英良が言っている。
清水は彼の実験劇団—解体社を始めた時、まず全ての自然主義的動きを除外した。「現実を見つめようとする芸術家は現実を見失い、単に幻想を模倣する」と彼は思っている。こうして役者と身体はオブジェと化した。松本雄吉の三次元巨大画のように。大阪の舞台建築家である彼は、1985年に維新派(更新の意)を創設した際、劇場も改良しようとした。彼は造形美術出身で、関西の具体グループの行動主義に影響を受け、壮大で音楽的な野外演劇を始めた。およそ50人からなる維新派の大集団は、様々な上演場所、使われていない鉄道やドックに、木造の宿を建て、厚板、柱などで巨大な舞台インスタレーションを造った。松本は清水同様集団と個人の記憶、歴史、大都市世界、日本独特の個の概念を考察している。松本の役者も、無名的(アノニマス)で、ユニフォームを身に着けており、機械オブジェのように共時的モーションで動いているように見える。彼らはユニバーサルな世界画画家のパレットの上の色であり、絵筆の一塗りなのである。
清水の軍需機器はしかしながら、戦いを仕込まれた人間の消えた顔の正体を明かす。役者は表現を意図して演じるのではない。それらは辱められたヒューマニティーや、利用価値を失って機能不全と化し、濫用されている身体の覆いの表現なのである。松本と反対に、清水は彼の「イメージの演劇」でその一歩先、「身体の演劇」へと、呼吸し出血し、汗をかいている身体へと進んだ。それは美醜の表面に固執するのではなく、身体の内側を外側に折り返そうとし、その疎外とデフォルメを残酷に暴露するのである。「批判するために、私は現存する(演劇、パフォーマンスの)構造内に、機能的混乱を造り出して、内的崩壊を引き起こしています。」「バイバイ/未開へ」では、一人の男性が鏡の前に立つが、それによって清水信臣は我々の前にも鏡を置く。男性は独りよがりに、西洋文化の業績であるαからΩまでのスペルを言い、通りすがりに戦いを企て、平然と叩き、続いてゆっくりマントを着、荷物をまとめて一度去り、ゆっくり無傷で戻ってくると、また服を脱ぎ、舞台上の戦争や生存競争がまるで彼には関係ないかのように落ち着いている。「バイバイ/未開へ」では、ほとんど目立たない冷笑する姿が端の方に。資本主義的力の黒幕、政治暴力を濫用するシニカルな抑圧的人物、しかし西側の文化過大評価の糸のもとでじたばたする悲しいあやつり人形。ボードリアールが彼のエッセイ“L'autre ailleurs”“Figures de l'atte'rite'”の中で記述しているように。
日本や他の文化は我々のものとは反対に、起源や信憑性のウイルスにおかされていないという。我々は、我々の文化は他の影響を受けずに自らの実在や実態を我々自身が創造したものだという原則を起点としている。「我々を苦しめた根本的な先入観です。」全てが我々から来ているという確信は「我々に起こったこと全てに全責任を取る」ということを強い、「そこに我々の悲惨が存在し、我々のそして西洋の不幸な運命なのである。」劇団解体社は、西洋のこの開いた傷口に、曲がって痙攣した指を静かに置くのである。
Ballet Tanz Aktuell International "Dance Becomes Politics" / Oct. 2001