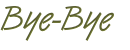劇団解体社にみる身体グローバリズムの暴力性
Marie Yereniuk
衝撃的であり、時に心を乱される劇団解体社のパフォーマンス「バイバイ/未開へ」は娯楽というよりも、むしろ強烈に惹き付けられる空間だ。その作品は、ダンス、演劇、電子音楽、そして、早送りの戦闘シーンのビデオ映写を合わせたもので、異質な、そして暗示的な雰囲気をかもし出している。この劇団は動きそのものを通して、より直接的な形でのコミュニケーションを主張しているため、言葉によるコミュニケーションはほとんどない。
上演に先立ち、東京大学の内野助教授は、劇団の演出家である清水信臣について「彼は決してアーティストなどというものではない」と語った。「彼は観衆にただの審美的な喜びを与える事には興味がない。」彼は人間の身体を、身体の内外に存在する暴力と破壊とのコミュニケーションの道具として表わす事に興味があるのだ。
清水のこの作品への創作欲を反映した「身体の暴力」はそのパフォーマンスの中にうかがわれる。断章の連続で構成されているその作品は薄暗がりと静寂の中で始まる。1人の女性がレオタードの下半身の部分だけを身につけて聴衆の前に立つ。彼女の全身は張り詰め、激しい振動に震え、機械かロボットを思わせる。清水の作品は人間の身体についてであるが、中嶋みゆきの震える胸と振れる手は人間のものとは思えない。
その女性は、聴衆から顔をそらしてじっと動かずに立ち尽くしている男性とともに舞台にたつ。彼の静けさは彼女の暴力的なまでの震えと好対照をなしている。二人は身体的にも感情的にも断絶している。パフォーマンス後の清水のコメントは、その部分を作品の文脈にそって理解させてくれる。その女優の動きは「自己と他者の境界を揺さぶるものであり、その境界そのものは崩壊している」のだ。境界線は消えてなくなりはしないけれども。
この比較的静的な部分はその後の動きの噴出のような部分へと続いていく。戦争のビデオ映像(偵察機群、爆発、そして流血)は不調和な電子音楽と合わさっている。それは衝撃的に残忍なムードをつくり出している。動物のような身体は舞台上を転がるように動き回る。その身体は肉体の狂乱の中でお互いにタックルしあい、取っては返している。それは、背景となっているイメージを象徴的に表現している。内野氏は「恐怖にかがみ込み、恐怖に苛まれながら、彼等の身体は戦争の機械としての役割を果たすようになっていく」と説明している。
個人と個人の暴力は全体に浸透したテーマだ。白人男性が金箔の帽子を被った日本人女性を平手で叩く場面がある。彼女は右手にナイフを持ってはいるが、その迫害者に対して報復しようとはしない。背中を叩く音は彼女の痛々しいうめき声よりもはるかに大きい。内野教授はこの場面を日本の植民地化の歴史を彷佛させるが、解釈は聴衆に任せられるものだと述べた。清水は「私がしようとしている事は一つの状況の提示だ」と強調した。「聴衆の思考を刺激したいのだ」と。 内野氏は「(清水は)彼自身に問いかける事、そして聴衆に疑問を投げかける事しか出来ない」と説明した。「彼はあまりにも挑発的だ。我々の感情に対しても、そして心情に対しても。」
清水とパフォーマ−は、死や残忍性を扱う現代日本の踊りの形態である舞踏で鍛えられてきた。清水はまた、プロットよりも役者の身体を強調する方式をとる1960年代アングラ(アンダーグラウンド)劇場に影響を受けている。しかしながら、内野氏によれば、解体社はそのジャンルには完全には当てはまらない。彼は、清水は「稀にみるグローバリスト」である一方、アングラ運動は「日本人らしさの捏造」であるという。彼の作品は人間についてであり、日本人についてではない。つまり、彼は国際的に、そして文化の枠を越えて、考え、行動し、演ずる事ができる人なのだ。
「バイバイ/未開へ」は戦争、大量虐殺、断絶といった普遍的な衝突を演じている。動き、静寂、そしてサウンドを通して、清水の振り付けはパフォーマンスアートの概念を再編成し、我々の住む世界に疑問を投げかけ続けるように喚起させてくれる。アートは常に美しいものなどではなく、常に示唆的なものなのである。
Colombia Daily Spectator (Oct. 2001)
The Violence of the Body Globalism in Kaitaisha Theatre
Marie Yereniuk
Although shocking and often disturbing, the Kaitaisha Theatre Company's performance of Bye-Bye: The New Primitive is less a piece of entertainment and more an intense and tantalizing ambiance. The work combines dance, theater, electronic music, and rapid video projections of war scenes to create an atmosphere that is both uncomfortable and thought-provoking. There is little verbal communication because the company advocates a more direct form of communication through movement itself.
Shinjin Shimizu, the company's artistic director, ''is by no means a kind artist,'' said Tadashi Uchino, a professor of the University of Tokyo who spoke prior to the performance. ''He is not interested in giving an audience sheer aesthetic pleasure.'' He is more interested in representing the human body as a tool for communicating the violence and destruction that exist inside and outside the body.
The ''violence of the body'' that influenced Shimizu's desire to create this work is evident in the performance. The piece, structured in a series of fragments, opens in near-darkness and silence. A woman faces the audience wearing only the bottom part of a leotard. Her whole body is tense, shaking in fine vibrations that are reminiscent of machines or robots. Although Shimizu's work is about the human body, Miyuki Nakajima's trembling breasts and shaking hands don't seem quite human.
The woman shares the stage with a man standing completely still, facing away from the audience. His stillness contrasts sharply with her violent shaking, and the two characters are isolated, emotionally as well as physically. Shimizu's comments after the performance helped put the section into the context of the piece: the woman's movement ''shakes the border between the self and other the border itself is disrupted,'' although it does not disappear.
This relatively stationary segment is followed by what seems like an eruption of movement. Video projections of war images--spy planes, explosions, and blood--combine with discordant electronic music to construct an atmosphere of shocking brutality. Creature-like bodies tumble onto stage, tackling each other and somersaulting in a physical frenzy, a symbolic representation of the images on the backdrop. ''Crouching over and jerking with fear, their bodies are intended to function as war machines,'' explained Uchino.
Violence between individuals is a pervasive theme. One scene shows a Caucasian man slapping a Japanese woman who wears a gilded helmet. Although she has a knife in her right hand, she does not retaliate against her oppressor, whose slaps to her back are much louder than her pitiful groans. Professor Uchino suggested that this might be reminiscent of Japan's history of colonization, but its interpretation is up to the audience. ''What I am trying to do is present a situation,'' emphasized Shimizu. ''I would like to provoke thoughts of the audience.''
''[Shimizu] can only ask himself and the audience questions,'' explained Uchino. ''He does so provocatively. Aristotelian catharsis is not operating here. Rather, we feel disturbed, in both our emotions and our minds.''
Shimizu and the performers were trained in Butoh, a contemporary Japanese dance form that often deals with death and brutality. Shimizu was also influenced by the Angura (Underground) theater of the 1960s that chose to emphasize the actor's body rather than plot. Yet according to Professor Uchino, Kaitaisha does not completely fit into this genre. The Angura movement was ''an invention of Japaneseness,'' he explained, while Shimizu is ''a rare globalist.'' His work is about being human, not about being Japanese; he is ''able to think, act, and perform internationally and interculturally.''
Bye-Bye: The New Primitive features universal conflicts such as war, genocide, and isolation. Through movement, silence, and sound, Shimizu's choreography realigns our concept of performance art, reminding us to continue to question the world we inhabit. Art is not always pretty, but it always inspires.
Columbia Daily Spectator / Oct.2001