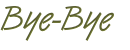性、身体、戦争群集、日本—解体の演劇
Randy Gener
ニューヨークでの9月11日の世界貿易センターテロアタックから一ヶ月もたたないうちに、東京を拠点とする解体社が、荒々しく肉体的、そして戦争に引き裂かれた作品、『バイバイ/未開へ』を上演することに、時期尚早すぎるという演劇批評家も必ずいるであろう。多分。確かにニューヨークでは、人々はまだ神経過敏になっている。アメリカ人の魂を悪寒で震わせた暴力、痛み、恐れは、観客を不快・不安にさせるのかも知れない。しかしながら、10月4日〜6日にJapan Societyのプロセニアム舞台で劇団解体社がみせた演劇パワーは、勇気があり無視できないものに感じられた。
アメリカのコマーシャル演劇が、世界的闘争時に戦争や暴力を直接的に扱った作品を敬遠するのに対し(例えばブロードウェイは、ステファン・ソンドハイムの「暗殺者」の再演を延期した)、不可能に挑戦し、言葉にできないことを言葉にし、言えないことを言うことが、ノン・コマーシャル演劇の必要任務になっている。これが、洞察的な清水信臣の率いる解体社の社会政治演劇がニューヨーク・デビュー公演で行ったことであった。
うずくまる身体、ふるえる肢体、変性意識、原子力爆弾といった、あふれる程のむき出しの自虐的イメージとともに、『バイバイ/未開』は、最も現代的な国際演劇の普遍化する衝動を提示した。言葉を回避し、ビジュアルを選ぶことで、言葉では何度やっても表現に失敗することをイメージで表現しようとした。コンテクストを取り除き、作品のテキストは超道徳性やニヒリズムといったテーマ(WORK NOT、BUY NOT、Hold a new weapon…)を喚起した。『バイバイ』には、ネガティブなアイディアを吐き出すという浄化効果がある。
パフォーマンスそのものは、あくまで「演劇」といっているが、実際はダンスの精神により近いものがあった。白人男性が灰色に塗った女性の背中を何度も叩き、打つ毎に日本の天皇の名前を呪う。美しい体型のアジア男性ダンサーの肉体は、作品の始まりに光の中でエロティックに表現され、肌が真っ赤に腫れ上がるまでドラムの音を出すように手で執拗に腿を叩き続ける。2つの世界大戦とベトナム戦争の映像が背景で流される中、暗い舞台上を肉体の固まりがよろよろ横切る。
『バイバイ』は不穏で張りつめたイメージをありありと提示する。純真に近い窮境の暗黒郷的ビジョン。ペースは意図的に作られている。解体社演出家の清水信臣は、ヨーロッパツアー開始当初の『バイバイ』は、もっとアグレッシブでアナーキー的だったとアフタートークで語った。ヨーロッパの観客の反応を見て、爆発的エネルギーを避け、よりゆっくりで透明、流動的な演出に変えたという。
プログラム上では、清水はアバンギャルド演劇の歴史に精通していることを示唆している。彼はアントナン・アルトーの"Theater of Cruelty"、ボニー・マランカの"Theater of Images"、ポスト大戦世界での伝統となった舞踏や、彼のいうところの、「現在の日本のトレンドである『生の演劇』」に精通している。彼は、「この作品は身体の演劇であり、『破壊欲求』に満ちています。その意味では、それは『死の演劇』といえます」と書いている。清水の学問的傾向はみごとである一方、作品を損なっている面もある。アフタートークでは(通訳的問題に耐えたにもかかわらず)彼のポストモダン演劇を明確化するのではなく、あいまい感、神秘感を残した。
ありがたいことに、作品が雄弁に語っていた。『バイバイ』は、演劇の過去の意識を明示し、将来の扉を開く個人的な道を達成する、清水の大変な努力を表象している。その中で、執拗にアバンギャルドな日本の劇団が、新たな表現方法を象徴的、演劇的に模索していた。それは20世紀社会のテクノロジー勢力が、いかに人間を植民地化し、暴行し、奴隷化し、襲撃しているかを示唆した、壮烈に露骨な作品である。それは、我々の身体への、繰り返されしつこく容赦ない攻撃に対処しようとする人間の苦労を演劇化していた。
『バイバイ』がパフォーマンスとして心を乱す作品であるなら、それはそれでよい。結局、挑発することは、真のヒロイックな演劇にとって必要な機能なのだ。さりげなく抽象的に、『バイバイ』は破壊された世界貿易センターの重みの下でつぶれた人間の残骸を演劇化している。大きな戦争マシーンの破片となったねじれた身体。『バイバイ』は、決して説教めかしたり単純化することなく、純粋な抗議のこぶしを振りかざしている。『バイバイ』は、反戦演劇をその黎明期の純粋状態に戻すことで、その比類ない強さを引き出したのである。
Culture Finder.com/ New York, Oct.2001