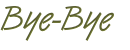歩行する病
カンプナーゲルの新たな始まり:ハンブルグ「ラオコオン」フェスティバル
Arnd Wesemann
コロンビアにある架空のある部族が、奇妙な病に取り憑かれている。眠ることができないのだ。日が他の所より8時間長く、手足が鉛の様に重く疲弊しているために、すべての動きが非常に遅くなってしまう。住人は白昼夢に甘んじている。仕事はすでに終わってしまったかのように思え、眠りそのものがいつも眠りに就いてしまっている。すぐに他の兆候も現れてくる。村中の人が、「かなとこ」や「戸」といった簡単な名前を忘れ始めたのだ。そこで当初村人は「かなとこ」や「戸」といった単語をメモに書き付け、物自体に張り付けて名前を忘れないように努めた。しかしながらその部族は、己の言語そのものを忘れ、メモを読むことすらできなくなってしまった。忘却とは、幸運である。舞台は、静かなる飢餓状態で終わる。
この物語は、コロンビアのコレオグラファー、アルバロ・レストレポによる驚くべき演技によって始まる。彼はコロンビアの血の混じる人々から神話を集め、それをダンスと語りを交えた一風変わった儀式形態で語り直した。マリー・フランス・ドゥリューヴァンは、ぞくっとする神聖なダンスでインディアンの創造神話を語る。褐色の肌をしたジェイエ・カンビンボは不思議な集中力を見せ、その筋骨たくましい体を黒く染め、アフリカの起源を夢見る。ロザリオ・ジャラミーオは赤いチュニックに身を包み、スタバート・マーテルの音色に乗せて、カトリックの征服者からブードゥーの司祭へと変貌する。アルバロ・レストレポは最終部で巨大なネットを使って、眠りに憑かれた手足を動かすかの様に静かに、日曜日の遅い目覚め様に怠惰にダンスをする。こうなると、上演時間は軽く4時間を超すことになる。
レストレポの演劇は安楽な夢中歩行であり、恐らくは初期の演劇史に印された極簡単な言葉を思い出そうとする試みなのだろう。「儀式」や、「ダンスによる解放」、「因習打破的な演劇」といった単語が忘れられて久しい。
カンプナーゲルの新時代を刻む初日は、93年にビアンカ・リーによってなされたコレオグラフィーで殊更穏やかに明けた。ベルリンのKomische Oper のマスターに新たに任命された彼女の舞台は、明らかに女性客のみを虜にしただけであった。『ナナとリラ』は、モロッコのバンドGnawa Halwaという陶酔的な火花をバックにしたビアンカ自身と他の8人の女性ダンサーのために、表向きワイルドな振り付けを施していた。男たちの音楽によって加速度がつき、ダンサーたちは恍惚状態に陥るものの、すべては管理され、事細かに計算され、厳密に動きが決定されていた。何の誤ちもないが、舞台はまるでクラシックの訓練を受けたバレエ・ダンサー演じるフラメンコのように見え、結果として初心者だけにエクスタシーを与えるものに見えた。
「何だこれは!」とカンプナーゲルの取り巻きは叫んだ。「大したものじゃないか、出鼻から」と常連客やスペシャリスト、スタッフといった、普段だったら怠惰に親指を上げ下げしてみせるだけの輩が腹を立てた。劇場が「彼/彼女たち」、つまり「全額料金の客」と呼ばれる観客のための作品で開いてしまったからである。ゴルダナ・フヌックは「彼/彼女たち」を挑発するかのようにかき抱き、ささやく。「魅了される必要もなければ、ダンス、アヴァンギャルド、実験的演劇といったものを教え込まれる必要もさらさらありません」。このやり方こそハンブルグ市民を満足させるものであり、市民が殊更気にかけている点である。
現時点において、8年前に創られ、オフ・オフシアターで上演された古い傑作に頼ることは、高額な補助金に支えられたレパートリー劇場にまで身を落とすことのように思える。しかしながら、赤い髪をしているからといって、ゴルダナが狡猾な狐という訳ではない。彼女はビアンカ・リーの作品でいわゆる大衆嗜好をなだめ、アルバロ・レストレポの作品で観客を夢が失われるまでの4時間のトランス状態に置く。彼女は観客を掴み、摘んだり抓ったりする。まさに、見ることの愉悦。そこへ日本のアヴァン・ギャルド集団、劇団解体社によって基本路線へと帰せられる。デュッセルドルフのタンツハウスと、フランクフルトのマーゾンタームでも9月半ばに上演される予定の作品『バイバイ/未開へ』は、文字どおり爆弾である。
劇中、灰色のネズミが完全な裸舞台に歩み出る。レンブラント風の金色の兜を被った少女の体は灰色に塗られ、ネズミの尻尾が下着に縫い付けられている。彼女は静かに舞台を横切り、ハラキリナイフを振り上げて、日本人にとっては地獄の三指令とみなされる「働くな、買うな、産むな」を吟唱する。この灰色のネズミは、世界のストック・シェアの動きに対応し、往々にして逃げ口上をとる島国同胞の危険な静止状態を管理するのに暇のないアメリカ人に監視されている日本人である。静寂の中、そんな同胞の心臓音を聞くことができるかもしれない。けれどもマシンガンの嵐が突如吹き荒れ、テクノの雷鳴が響き、アメリカの国旗とともに戦車や原子爆弾のビデオ画像が始まる。内へと向かう自己消費的な恐怖という信じがたいスタッカートの中で、全てを貪り尽くす戦争が繰り広げられる。
劇団解体社は、目下最も重要な日本のアヴァン・ギャルド集団である。その作品は、ヤン・ファーブルの白黒の初期作品の一つを想起させる。演出家清水信臣も白黒と沈黙を使っているが、直ぐさまそれらは音響によって引き裂かれる。ダンサーたちは震える脅威であり、立ち尽くす肉体であり、帝国主義的な敬礼をするために掲げられる腕である。劇団解体社が初めてヨーロッパを訪れ、ゴルダナ・フヌークが未だ支配していて今後も監督していくであろう、かの地ザグレブで行われたユーロカズ・フェスティバルでスキャンダルを巻き起こしたのが、1996年である。その時は観客が舞台に押し寄せ、ダンサーたちを保護しようとした。なぜならむき出しの腿や背中を半時間以上掌で打ち続け、表皮から血が浮き上がる程であったからだ。今回、清水信臣はそこまで極端に行くことはないかもしれない。だが、この作品は、カンプナーゲルが将来再び国際的なアヴァン・ギャルド演劇の中心となることを確信させてくれるだろう。
Süddeutsche Zeitung紙 (3/Sept. 2001)