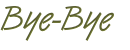廃墟の中の身体
アルバロ・レストレポと劇団解体社—カンプナーゲルにて
Marga Wolff
現代演劇における身体の誕生、消滅、再生についての講義が、演劇批評家であり来期のラオコオン・フェスティバルのキュレーターである鴻英良によってなされた。今日劇場に溢れているのは、傷を負い、病んだ身体である。エイズの身体、遺伝子の組織体系にまで科学的に類別されてしまった身体、物理的にも精神的にも解体され、時空間に関わりなく勝手に動き、孤独かつ冷酷であり、侍の精神力によってコントロールされている身体。
「劇場は戦場である」と演出の清水信臣は語る。男女10人のダンサーから成る劇団解体社は、『バイバイ/未開へ』において、この世の戦争のすべては彼・彼女らの体に深く染み込んでいるかのようなイメージを伝えている。東京から来た劇団解体社のフィジカル・パフォーマンスと、ワールド・プレミアであるアルバロ・レトロスポの美しい夢の世界『テトラロジアーコロンビアの一風景』は、不手際に終わったラオコオンのオープニングを埋め合わせ、カンプナーゲルにおけるゴルダナ・フヌックの方針を見事に指し示していた。
劇場空間の静寂は重苦しい。目隠しをした男が、手錠をかけられたまま、微動だにせず立っている。押さえ込まれたその体は闇の中で呼吸し、女の痙攣的な動きからもたらされる震動を吸収してしまうかのようだ。本能的に動き、猫の様にしなる彼女は、しばらくの間四つ足で歩く。あたかもその体が千個の新たな断片へと再組織されてしまったかのように—そしてそれらの断片は、多分はもう二度と認識されることはないのだが、がたがた、ぴくぴくと立っている。
男の方へと向かう女の道も閉じられている。登場人物達は幽霊のごとくゆっくりと動く。無表情な顔つきは、痛みと苦しみに関するすべてを知り尽くしてしまったかのようだ。内へと歪む手足は、時に舞踏を想起させるが、15年前に旗揚げされた劇団解体社の手法は、西洋現代ダンスのコレオグラフィック言語により近く、それらを切り詰めた形で用いながら様々に応用している。
耳をつんざくようなノイズが、死んだような沈黙を破る。次に兵隊や戦闘機、投下される爆弾といったイメージが明滅する。戦争の神であるマルスは女性によって表象され、羽のついたかぶとを被って劇場を旋回する。血塗れの兵士が彼女の灰色の背中に加える強打でさえ、彼女を止めることは出来ず、受け入れられることもない。犠牲者も加害者も清水信臣のアレゴリカルな世界観においては悼まれることはない。世界観そのものは、非常に敏感なパフォーマーの身体によって表明されるのみである。強い照明の下、張りつめて震える身体は、荒廃した風景のようにも見えると同時に壮烈に強く、また哀れにも弱々しいものにも見える。
身体の脆弱さは、アルバロ・レストレポがその世界像の源としているものでもある。だが彼は、劇団解体社が意図的に引き裂いた傷を癒したがっている。観客は魔法のような景観によって場面が開けた瞬間、息を飲んだ。かのコレオグラファーは、その神秘的なヴィジョンを舞台上に植え込んでいた。闇の地に砂でできた迷宮が浮かび上がる。光が天井から水滴のように垂れ落ち、それらの仄かな輪が決まったリズムで中頃から先端へと流れていく。音と歌が空間を満たし、芳香と溶け合う。声が水から生まれた世界創造の話を語る。この古のインドの神話は『蛇のカヌー』と呼ばれるものである。
ダンサーのマリー・フランス・ドゥリューヴァンは小さなガラスの瓶に満たされた青く閃くボートに乗り、その膝に水晶体を置いている。レストレポは、照明のセルジオ・ペッサンハの助力を得ながら、魂の風景を描き出す。浅黒い肌を持つダンサー、ジェイエ・カンビンボは、この大地をまるで野良猫のように歩き廻る。彼は猟師から兵士へと変化し、ついには獲物そのものとなってしまう。夜のごとく肌を黒く彩り、赤い印をその奴隷の胸に付け、血に染まった心臓が脈打つ大地と一体化する。--母であり、娼婦であり、聖処女であるスタバート・マーテル。
女優ロザリオ・ジャラミーオは、グロテスクなブードゥー教の魔女の姿でカトリック教会の苦行にあらがう。赤色に覆われながら、彼女は自らドレスを引き裂く。ライトがその白い胸を照らし出す。レストレポはこの場面において、単に異文化間の和解に留まらない人間性の奥底に迫る何かに触れていた。レストレポ自身は4部からなるソロ・ピースの最後に巨大な藁帽子を被ってダンスをした。彼は運動と未来について語っているのだ。
taz Hamburg紙 (3/Sept. 2001)