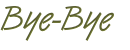危機的状況をみつめる視座
変わった米観客の精神性
内野 儀
社会が危機的状況に陥ったとき、芸術に、たとえば演劇というメディアに何ができるのか?日本とアメリカでの答えはおそらくこうだ。何もできはしない。芝居なんか見ている場合じゃないんだから、と。事実、阪神大震災後に関西地区で上演された演劇は、妙に明るい内容のものばかりだった記憶がある。地震という自然現象の場合、「事後」は復興しかないのだからそれも理解できないわけではない。だが、先が見えない危機的状況の場合はどうだろう?
ボスニア内戦のとき、攻囲されたサラエヴォでは二つの伝説的な演劇上演があった。一つはアメリカの批評家・劇作家スーザン・ソンターグによるベケットの『ゴドーを待ちながら』、もう一つはアメリカの小説家ポール・オースターの『最後の物たちの国で』を戯曲化したものの上演である。両作品は先が見えない不条理で危機的な世界を描いた二〇世紀の傑作である。いつ終わるともしれない追いこまれた状態にありながら、サラエヴォの人々は、一時的に恐怖を忘れるための明るいエンターテイメントを求めなかった。そのかわりに、自分たちの「出口なし」の状況を的確かつ普遍的な視野から描いた二作品を共に見るという経験を選んだのだ。「私たちのこと」を描いた作品を見ることで過酷な現実に向き合うための別の視座を獲得しようとしたのである。
今回のアメリカの同時多発テロ事件の場合はどうだろう? 当然のように、ニューヨークのブロードウェイは大きな打撃を受けている。「芝居なんか見ている場合じゃない」のだ。「劇場へ行こう」というかけ声はあるものの、なかなか客足は戻らないのである。残念ながらブロードウェイでは、「私たちのこと」を描いた作品を見ることはできない。そこで上演されているのは、大抵の場合、「かつての私たちのこと」でしかないのである。そこに偶然、「私たちのこと」を描いた演劇が登場した。いや、してしまった、というべきだろう。特異な身体表現で知られる日本の劇団、解体社が十月初旬、初のニューヨーク公演で『パイパイ−−未開へ』という作品(十月四日~六日、ジャパン・ソサエティ)を上演したのである。
ただ微妙に痙攣して崩れてしまう身体。片腕を上下させるという動作をひたすら繰りかえす身体。男優に背中を殴打される女優の身体。こうした様々な身体のあり方が、そのまま舞台に陳列される。
構成・演出の清水信臣によれば、この舞台の主題は同時代の身体のあり様を描くことにあるという。彼はそれを「攻囲された身体」と呼ぶが、それはサラエヴォのような紛争地帯での破壊や死を恐怖する身体を意味するだけではない。我々の身体は過剰な情報に攻囲されて身動きできない。あるいは、崩壊寸前の旧来的システム(たとえば「日本」というシステム)は、我々の身体を極限まで攻囲し=追込み、引きこもりからテロ攻撃まで、自己や他者への暴力の発動を促してしまう。
この作品は今年六月に東京で初演されたもので、ニューヨーク公演のために作られたものではない。しかし、公演後の観客との質疑応答の中で「あれは私たちのことだ」と清水に語った観客がいたことに、私は複雑な思いを抱くことになった。次なるテロヘの恐怖に揺れるニューヨークの人々の心と身体のあり様を、清水は期せずして舞台に提示し、共感を勝ち取ってしまったのである。それを芸術の勝利などとはいうまい。世界で起きつつあること、我々の多くには見えていないが、見えない部分で起きつつあることに清水の想像力が及んでいたことを証明したにすぎないからである。
サラエヴォとユーヨークの状況は相当にちがう。解体社の公演を見た観客はニューヨーク市民のほんの一握りにすぎないし、大きな影響力を持ったとも思わない。だが、自己の想像力のあり方が正しかったことを日本の劇団である解体社のメンバーたちが知ったことは重要であると思う。「あれは私たちのことだ」と評価されることほど、アーティストを勇気づける言葉はほかにない。とりわけ、先が見えない危機的状況においては。
毎日新聞 夕刊 2001年11月8日