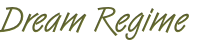[…]ではなぜ、この『荒れ野の40年』のようないわば近代国家を超克したような追悼演説が生み出されたのでしようか。以前は「国益を第一に考えた保守政治家としての普通の行為」として扱ったのですが、911以降の世界──「戦争の世紀」の再来のなかではそのようには片付けられないのではないか、そう思いながら、今回、再びヴァイツゼッカーを読み返すとき、キリスト者というものが強烈に出てくる。おそらく彼にとっては信仰が認識の基盤であり「反省」はそこから直に現れる。たとえば演説では「心に刻む」という言葉が幾度となく言われるのですが、それは「ある出来事が自らの内面の一部となるよう、真誠かつ純粋に思い浮かべる」ということです。「六〇〇万のユダヤ人、ソ連、ポーランドの無数の死者、虐殺されたジンティ、ロマ、殺された同性愛の人びと、殺害された精神病患者、宗教もしくは政治上の信念のゆえに死なねばならなかった人びと、銃殺された人質、はかり知れないほどの死者のかたわらに、人間の悲嘆の山並み」を「心に刻む」ということ──それは「歴史における神の御業を目のあたりに経験すること」でもある、と言うわけですが、つまりそれこそが本当に「弔う」ということであって、それは刹那も途絶えることのない「喪の行為」であり、いわば「際限のない喪、無限の喪」(デリダ)、なのだということですね。ですから、国が、墓所(追悼施設)を造って年に一度お参りするなどということではまったくない、つまりこの行為は(トラウマ)記憶から癒されるための「お参り」ではない、ということ──今回の上演『夢の体制』の第一部の『信仰体』ではこの「信仰」と「反省」の意味するものを『モーセと一神教』(フロイト)を解読格子に使いながら問うてみたかった。
上演ではドイツの女優が(この演説を)歌うように姿見(鏡面)に向かって発語する。そこにポーランド、韓国、日本の女優たちも加わってもらい、自国の歴史・文化についての「反省」を行いながら、各々の置かれている現在について舞台上で(演技を中断し)議論するシーンを創ることにしました。
第二部の「『病者』の時代」では、現在トレンドとなっているデザイン工学・環境管理型の権力が問題化されています。全ては都市工学的な思想でもって統治=動物化できうるという悪夢、あるいは、それら新たな権力によって生政治空間の外へと放擲される「病者」への接近が試みられます。──具体的には、グダニスク市(ポーランド)にあるドラッグ中毒更正施設にいる若い人たちに出演してもらいました。そこでは自分たちの境遇を告白するシーンの映像が流されるのですが、彼/彼女らの中毒者としての告白はとても苦しいものですし、「身振り」もまた自らの苦悩の体験をまさに「心に刻んでいる」かのように、つまり「反復」しているかのようにみえるのです。けれどもその「反復」はヴァイツゼッカーのように決して「力強く」はありません。弱々しい、後ろめたい、消え入りそうなそれは「身振り」なのです。
「病者」は、いわばラカンのいう「アーテー」においてしか生きられぬ者です。それらは「アーテー」を欲しない者たちによって忘れられ(る)たがゆえに、「救済を拒絶する者」になるのです。この事態によってもたらされる「悲劇」、それが『夢の体制』ー「病者」の時代ーを貫いています。
清水信臣 (劇団解体社/演出)